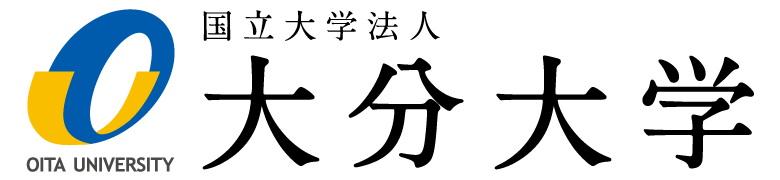-
日田市天ヶ瀬温泉地区における災害時の避難訓練に協力
2022年6月17日(金)
減災・復興デザイン教育研究センター(以下,減災センター)は,6月5日,NPO法人リエラと共に日田市天瀬振興局と住民主体の組織「天ヶ瀬温泉つなぐ会議」が実施した天ヶ瀬温泉街一斉避難訓練に参加しました。 この避難訓練では,日田市や地元関係機関と連携し,避難行動に対するヒアリング調査や学生CERDも調査を実施した。あいにくの雨にも関わらず55世帯82名が参加しました。調査では,82名の参加者のうち67名から回答があり,避難所までの時間や交通手段を確認するとともに,避難するタイミングや避難指示における放送発令等の聞こえやすさ,近所への声掛けなどの初動対応,避難先や避難所の課題などを把握しました。昨年度からの改善点もみられましたが,新たな課題が見つかるなど,避難所運営の難しさを感じました。 避難訓練には減災センターのスタッフに加え,本学が実施している重点領域研究推進プロジェクトの1つである「自然災害時の避難所における健康危機管理」の研究チームの教職員も参加し,研究という視点から実際の避難訓練を見学しました。 令和2年7月豪雨で甚大な被害を受けた天ヶ瀬温泉街では,地域の方を中心に日田市と連携して様々な復興事業が進んでいます。減災センターでは引き続き,災害ボランティアの派遣や復興支援を行っていく所存です。 学生CERDによるヒアリング 研究チームよるヒアリング
-
学生災害ボランティア講習会を実施しました
2022年6月17日(金)
減災・復興デザイン教育研究センター(以下,減災センター)は,6月1日にオンラインによる学生災害ボランティア講習会を学生・留学生支援課と共同で行いました。本学学生が実際に被災地へ災害ボランティアとして参加・活動をする場合は,本講習を毎年受講することが条件となっており,約100名の学生が受講しました。 初めに,本学OBのNPO法人リエラ代表理事の松永さんから災害ボランティアの必要性や心構えについて,東日本大震災における自身の経験を踏まえ説明がありました。次に,学生CERDの代表である理工学部2年大賀さんが,ボランティアの経験談や自身が活動している学生CERDの紹介を行いました。大賀さんは,東日本大震災をきっかけとして“自分にできること”を考えはじめ,様々なボランティア活動に参加し,令和2年九州北部豪雨の際は,久留米市で災害ボランティア活動に従事しました。「どんな人でもできることがある。ぜひ,難しく考えずに災害ボランティアに参加してほしい」ということを講習会に参加した学生に伝えました。 さらに,医学部(減災センター兼担)の下村剛教授から,医学的な見地に基づき,災害ボランティアにおける感染症対策について説明がありました。最後に,5月25日に行った尾畠さんによる土のうつくり講座の映像を流し,尾畠さんから「まずは自分の命と家族と自分の家を一番に守ることが大事。それが確保できれば困っている人のところに手を差し伸べてもらいたい」という言葉がありました。 本学では,災害ボランティア活動に関しては組織的な対応を軸としています。災害ボランティアの派遣では,減災センターが現地の安全を確認するとともにボランティアセンターとの調整を行い,学生・留学生支援課を通じて講習会受講者へ参加案内します。最終的には派遣の有無を学長が機関決定し,被災地へ災害ボランティアを大分大学として派遣します。 新型コロナウイルス感染拡大の影響により県外から参加する災害ボランティアの協力が難しいため,早期の復旧・復興には県内の総力が必要とされています。講習会で得た災害ボランティアの知見を活用して,本学でも被災地で行う活動に迅速に対応し,機能的な対応をしていく所存です。 オンライン講習会の様子
-
地理空間情報活用推進に関する大分地区産学官連携セミナーのお知らせ
2022年1月11日(火)
地理空間情報活用推進に関する大分地区産学官連携セミナー ― 地理空間情報が担う安心・安全な地域社会の構築に向けて ― 詳細資料はこちらから <開催趣旨> 近年の災害では、これまでの想定を超える深刻な状況が頻発しており、行政の支援に頼るだけでは、対応に限界があると思われます。災害から身を守るためには、住民自身の自助能力と地域の互助能力が不可欠であり、そのためには、行政・専門家・企業・住民が共にリスクについて意見や情報を交換し、相互に意思疎通を図る「リスク・コミュニケーション」が不可欠と考えます。地理空間情報は各種情報を活用し地域のリスクを一元化・見える化を図ることにより、分析・予測が可能になり、リスク・コミュニケーションの有効なツールとなります。 今回のセミナーでは、防災や減災をテーマとした大分県の産学官による地理空間情報の活用事例を紹介し、地理空間情報の高度活用社会と課題について議論します。皆様のご参加をお待ちしております。なお、セミナーは一般社団法人地理情報システム学会による「GIS DAY in 九州 2021」の公式イベントです。 <開催日> 2022(令和4)年2月4日(金) 10:00~12:30 <会 場> J:COMホルトホール大分小ホールより オンライン開催(Zoomウェビナー) ※協議会関係者以外は会場に直接参加することはできません。 <参加費> -無料- 個人、法人問わずどなたでもご参加いただけます。Zoomウェビナーへの接続 については申込頂いたメールアドレス宛に、2月2日(水)頃にお知らせいたします。 <申込方法> 下記の①②のどちらかの方法でお申し込みください。 2022(令和4)年1月28日(金)までにお申し込みください。 ①お申込みフォーム https://forms.gle/mYMK5V7BXLiwdSiKA ②お問合わせ先まで以下の項目を送信してください。 氏名・所属・メールアドレス <主 催> 地理空間情報活用推進に関する九州地区産学官連携協議会 地理空間情報活用推進に関する大分地区産学官連携検討会 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター【CERD】 <共 催> 大分県、日本文理大学、独立行政法人国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校、一般社団法人 大分県測量設計コンサルタンツ協会、おおいた建設人材共育ネットワーク【BUILD OITA】、一般社団法人 地理情報システム学会、GIS基礎技術研究会 <後 援> 国土交通省国土地理院 <お問合せ先 または メールでの申し込み先> 地理空間情報活用推進に関する大分地区産学官連携協議会 事務局 事務局:宮元 昭彦(国土地理院九州地方測量部 地理空間情報管理官) E-mail:gsi-sangakukan-9【アットマーク】gxb.mlit.go.jp ※メールアドレスのスパム対策のため,アットマークを変換して送信してください。 <プログラム> 詳細資料はこちらから 大分地区産学官連携検討会による活動報告 一般社団法人 大分県測量設計コンサルタンツ協会 理事 吉田 靖 大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター 次長・教授 鶴成 悦久 日本文理大学 工学部建築学科 環境・地域創生コース 教授 池見 洋明 大分工業高等専門学校 都市・環境工学科 准教授 前 稔文 大分県 生活環境部 防災対策企画課 防災対策班 主任 阿部幸平 大分県 商工観光労働部 先端技術挑戦課先端技術挑戦班 主幹 本田 真也 大分県 土木建築部 建設政策課 主査 築地 祐一郎 パネルディスカッション「強靭な県土づくりに向けた地理空間情報の活用」 (ファシリテーター) 鶴成 悦久(大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 次長・教授) (パネリスト) ・九州地区産学官連携協議会 三谷 泰浩(九州大学 大学院工学研究院 教授) 檜山 洋平(国土交通省国土地理院 九州地方測量部 部長) ・大分地区産学官連携検討会 吉田 靖(一般社団法人 大分県測量設計コンサルタンツ協会 理事) 池見 洋明(日本文理大学工学部建築学科環境・地域創生コース 教授) 成瀬 哲哉(大分県 土木建築部河川課 課長)
-
年末年始の休業について
2021年12月27日(月)
大分大学では令和3年(2021年)12月28日(火) にかけて一斉休業のため,本年のセンター業務は12月28日(火)までとなります。 業務につきましては令和4年(2022年)1月5日(水)からとなりご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 本年は大変お世話になりました。 来年もよろしくお願いいたします。
-
『大分県災害データアーカイブ』リニューアルバージョンの公開
2021年12月24日(金)
減災センターではNHK大分放送局と共同で開発する『大分県災害データアーカイブ』のリニューアルバージョンを公開しました。 今回のリニューアルではタブレットやスマホでの利用を視野にデザインされ,検索やマップ表示機能が改善されました。 ※令和3年2月18日にURLを変更しました。 <大分県災害データアーカイブ> 大分県内の文献を用いて大分県内で発生したおよそ1300年間の災害の記録をまとめたものです。 https://archive.cerd-edison.com/ <大分県災害データアーカイブ ポータルサイト及び映像ライブラリー> NHK大分放送局で放送された『大分県災害データアーカイブ』関連番組や,過去の災害の映像を見ることができます。 https://www.nhk.or.jp/oita/saigai-data/index.html トップページから過去の災害写真やエリア,現在位置から過去の災害を検索することができます。 今の季節(月)と同時期に発生した過去の災害事例を表示しています。 検索画面から「マップを見る」ことで過去の災害を地図で表示します。左上のアイコン「MAP」より地図の種類やハザードマップを表示することができます。また,右の項目から災害の詳細ページを開くことができます。なお,表示される災害個所(位置)は発生個所をおおよその範囲でしめすものであり,必ずしも過去の災害個所と一致しているわけではありません(誤りもあります)。 災害情報の詳細が表示されます。なかにはNHK大分放送局がもつ過去の映像や,文献や個人から提供頂いた写真が表示されます。
-
ボウサイ・ゲンサイ教育の座談会LIVEを開催します
2021年11月25日(木)
お題のない座談会なのですが,ボウサイ・ゲンサイ教育についてちょっとワイワイ語りませんか?っていう漠然とした企画です。 平日の夕方6時から9時くらいまで,出たり入ったりって感じで参加してみてください。 学生さんも子ども達も大歓迎です。ラジオを聴くようにどうですか? とりあえずは,どなたでも参加できるというのがウリです。 大分県内ではこんな感じのことはあまりしていなかったような気がしますね。 皆さんの思いとか心配事を共有しませんか? 大分のこれまでとこれからを語るのです。 詳細については、 ボウサイ・ゲンサイ教育の座談会LIVEをご覧ください。 開催日時:2022年1月19日(水) 開始18:00 21:00終了 【申込フォームはこちら】
-
令和3年度別府市鶴見岳赤池噴気孔の調査結果について
2021年11月2日(火)
別府市では関係機関との連携により鶴見岳山頂付近の地獄谷赤池噴気孔(「鶴見岳・伽藍岳」噴火警戒レベル1)の調査を毎年実施しています。減災センターにおいても令和元年度より調査に参加し,別府市(市,警察・消防)や大分県(防災局,砂防課),気象庁(福岡管区気象台,大分地方気象台),とともに,UAV(無人飛行機:ドローン)に搭載した赤外線カメラを利用して噴気孔や地熱の分布状況を観測しています。 ※国有林野内で無人航空機(ドローン等)の飛行については森林管理署等への手続きが必要です。 11月1日(月)に実施した本年度の調査では,赤池噴気孔周辺部における地熱分布及び噴気孔の確認とともに鶴見岳東側一帯の新たな地熱帯の確認などを行った結果,2020年の調査結果と比較し特段の変化は確認できませんでした。この他,別府市消防本部では火山性ガスの計測,気象庁では地表面温度測定などを行っております。 <赤外線ドローン撮影による動画:2021.11.1> [embed]https://youtu.be/MTxNIe14-qo[/embed] <参考>鶴見岳の様子(2019.9.19) 鶴見岳噴気孔の様子(YouTube動画) 鶴見岳地獄谷赤池噴気孔周辺地形(三次元データ) <2021年 令和3年11月1日調査結果> 2020年調査結果はこちら
-
複合的な災害への備えと対策を考えるオンラインシンポジウム 「災害に備える新しい社会のカタチ」
2021年10月20日(水)
複合的な災害への備えと対策を考えるオンラインシンポジウム 「災害に備える新しい社会のカタチ」 感染症、自然災害などの多様な脅威にどう備えるか? 大学改革を通じた地方自治体との協働体制の構築に向けて 新型コロナウイルス感染症の世界的流行拡大や、豪雨災害、さらには今後発生が想定される南海トラフ地震等、大分県は感染症や自然災害の脅威に直面しています。 大分大学は 2018 年 1 月に「減災・復興デザイン教育研究センター(CERD)」を新設し、2021 年 10 月には「グローカル感染症研究センター」を設置しました。 このシンポジウムでは大分大学のこれまでの活動と、感染症など複合的に考える必要のある問題をこれからも地域と協働し、どのように地域貢献を行っていくのかを議論します。 詳細はこちら 開催日時 令和3年11月20日(土)14:00~16:30 ※要事前申込 ※参加無料 開催方法 オンライン開催(zoomウェビナー) 基調講演 「県内における新型コロナウイルス対策 これまでとこれから」 (大分県福祉保健部 理事兼審議監 藤内修二) 「日常と非常時のフェーズフリー」 (大分県生活環境部防災局長 梶原文男) 事例紹介 「グローカル感染症研究センターの目指すもの」 (大分大学 グローカル感染症研究センター長 西園晃) 「減災社会に向けた減災・復興デザイン教育研究センターの取り組み」 (大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター 次長 鶴成悦久) 「動物に由来するハザード -外来種の脅威-」 (大分大学 研究マネジメント機構 助教 奥山みなみ) パネルディスカッション 「感染症、自然災害などの多様な脅威にどう備えるか」 <ファシリテーター> 西園 晃 (大分大学 グローカル感染症研究センター長) <パネリスト> 藤内修二(大分県福祉保健部 理事兼審議監) 梶原文男(大分県生活環境部防災局長) 坂本照夫(大分大学 医学部附属病院高度救命救急センター長) 鶴成悦久(大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター次長) 問い合わせ 大分大学研究推進部研究推進課 TEL:097-586-5409 E-mail:glogal【アットマーク】oita-u.ac.jp
-
令和3年度日本学術会議 九州・沖縄地区会議 学術講演会「持続可能な地域の強靱化と将来空間像 ~防災・減災対策の次なるステージを目指して~」
2021年10月19日(火)
自然災害が多発する今日,防災・減災対策の次なるステージを目指し,安全・安心で持続可能な地域社会,地域空間を形成するための強靱化やまちづくりの方向性,そして長期的な視点に立った将来的な国土・地域空間のあるべき姿について議論を行います。 【本学教員発壇者】 ・減災・復興デザイン教育研究センター長 小林 祐司 ・経済学部教授 宮町 良広 ・医学部教授 三重野 英子 開催日時 令和3年11月1日(月)14:00~16:10 ※要事前申込 ※参加無料 開催方法 オンライン開催(Zoom) 問い合わせ 大分大学研究推進部研究推進課 TEL:097-554-7111 E-mail:kenkyou【アットマーク】oita-u.ac.jp ※申し込み方法は,下記詳細をご参照ください。 詳細はこちら
-
大沢京都大学教授 客員教授就任のお知らせ
2021年10月1日(金)
令和3年10月1日付けで減災・復興デザイン教育研究センター客員教授に京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設(別府市) 教授 大沢信二先生が就任されました。 減災センターでは大沢教授と大分県内における火山防災への取り組みを進めております。特に鶴見・伽藍岳(別府市)における火山災害に関しては関係機関との連携を強化し,多面的な角度から起こりうる火山災害と地域特有の課題を探り,減災社会実現と火山防災に向けた取り組みを強化していきます。