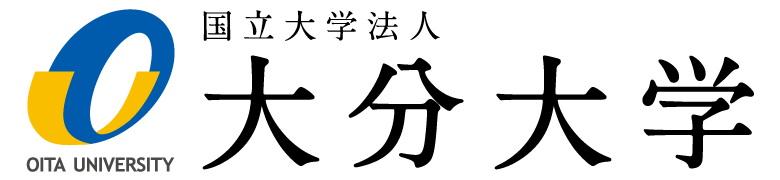センター長 挨拶
全国規模で多発化・激甚化する自然災害は,従前と異なる想定をはるかに超え,我々の身近な場所でいつ・どこで発生しても不思議ではない時代へとなりました。大分県内でも梅雨期や台風の接近により度重なる風水害に見舞われており,平成28年熊本地震では大分県内でも甚大な被害が発生しました。また,南海トラフ地震や中央構造線断層帯,そして周防灘断層帯による大規模地震や津波災害への備えは大分県にとっても重点課題の一つでもあります。加えて,国内有数の温泉地でもあると同時に鶴見岳・伽藍岳,由布岳,九重山の活火山を抱えており,火山災害に対する対策も近年高まりをみせています。これら自然災害に対する安全・安心な社会の構築に向けて,ハード及びソフトの両面において防災・減災対策,国土強靭化の取り組みが進んでおり,地域にとっても大きな関心が寄せられています。一方で,来るべき自然災害を迎えながら現代社会を生きていくことは,我々一人ひとりの共通の課題でもあり,防災や減災が主流となる社会を構築するためにも,地域社会が一体化しこれらの課題に取り組む必要があります。
本学では近年の自然災害への発生を踏まえ平成30年1月に「減災・復興デザイン教育研究センター(CERD:Center for Education and Research of Disaster Risk Reduction and Redesign)」を設置しました。センターは地域の安全・安心社会への構築に寄与すべく「調査研究」「防災教育」「復興デザイン」を大きな柱として地域社会と緊密に連携しながら教育研究活動を行なっています。センターは平成29年6月に大分大学認定研究チームBURSTとして認定を受け,平成29年7月九州北部豪雨及び平成29年9月台風第18号への対応を皮切りに,学長のリーダーシップのもとで学内共同教育研究施設として新設されました。センター発足以降,平成30年4月に中津市耶馬溪町金吉で発生した大規模な山地崩壊では,中津市からの災害派遣要請を受けて,現地対策本部にて捜索救助活動への指導助言を実施。令和2年7月豪雨では大分県と連携し日田市の災害対策に関する助言を行うほか,被災地への支援物資の提供や災害ボランティアの派遣を実施しました。また,地域社会が求める防災・減災へのニーズに応えるため,地域が行う避難訓練や自主防災会活動,学校で行う危機管理や防災教育への活動支援を行なっています。さらに災害を想定した復興のビジョンを共有化するとともに,被害の最小化を目指したまちづくりを推進するため,被災地の復興計画をはじめ,火山災害や地震・津波に対する事前復興への活動を支援しています。
センターは主担当教員,防災コーディネーター,事務スタッフ,全学部を通じてセンターを兼務する兼担教員に加え,学外の客員教授・准教授,客員研究員で構成されており,多様な研究人材により教育研究が進められております。また国や地方公共団体をはじめ,大学,企業やNPOなど防災や減災に関する連携や協定を締結しており,災害時対応だけでなく平時の防災・減災活動を協働で実施するなど,緊密な連携活動を図っております。大分県とは平成31年2月に「災害対策に係る連携に関する協定」を締結し,県内の地方公共団体(県も含む)に対する災害対応業務の高度化の推進等に資することを目的とした連携事業を進めております。なかでもセンターが進める災害情報活用プラットフォーム(EDiSON:Earth Disaster Intelligent System Operational Network)では,教育から対応そして復旧や復興に関する災害に関する一元的な情報の集約と活用を目指すため,大分県と連携し社会実装を進めています。これらセンターと大分県はEDiSONを基盤とする防災DXの推進を図り,災害対応への高度化とともに地域防災に資する諸活動を実践しています。
一方で新型コロナウイルスによる新興感染症の流行は社会全体へ大きな不安を与えました。自然災害も同様に消し去ることのできない未知なる脅威として存在する中で,これらが同時期に発生するマルチハザードへの対応は重視されるようになりました。そこで本学では減災・復興デザイン教育研究センター,グローカル感染症研究センター,医学部附属病院災害対策室/高度救命救急センターが中心となり,令和4年4月にクライシスマネジメント機構を設置しました。クライシスマネジメント機構では防災・減災,感染症対応,災害医療,福祉健康分野の有機的な連携によりマルチハザードへの対応を強化することと同時に,関連する情報を一元的に集約し活用する取り組みを進めています。センターでは従来の活動に加え,災害発生時における医療や感染症に対する取り組みを進めると同時に,避難所における様々な健康課題に対処するためのプロジェクト(代表:徳丸治教授 センター兼担・福祉健康科学部)を実施しています。
多様かつ複合的な災害への備えが求められる中,センターは大分県の防災・減災の中核的組織としてさらなる機能強化を図ると同時に,地域の様々な課題の解決や持続可能な社会のあり方を提案,推進できるインテリジェンス・ハブとしての機能を高め,安全・安心な社会の構築に寄与していく所存です。
令和4年10月 減災・復興デザイン教育研究センター長 鶴成 悦久
減災・復興デザイン教育研究センターの沿革
| 2017年3月 | 大分市と災害に係る協力体制に関する協定を締結。 |
| 2017年6月 | 大分大学認定研究チーム(BURST)の制度により,「減災・復興デザイン教育研究センター(CERD)」が認定,設置。 |
| 2018年1月 | 学内共同教育研究施設「減災・復興デザイン教育研究センター」が設置(※研究チームが常設センターへと移行) センター長に西園晃理事(研究・社会連携・国際担当)が就任。 |
| 2018年4月 | 国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所と連携及び協力に関する協定を締結。 |
| 2018年4月 | 佐伯市と「災害に強いまち(人)づくり」に関する協定を締結。 |
| 2018年4月 | 中津市耶馬溪町大字金吉で発生した大規模な土砂災害対応のため中津市長からの要請によりセンター教職員を現地対策本部へ派遣。 |
| 2018年8月 | 株式会社大分放送(OBS)と連携及び協力に関する協定を締結。 |
| 2018年11月 | 国立大学法人九州大学大学院工学研究院附属アジア防災センターと連携及び協力に関する協定を締結。 |
| 2018年12月 | 大分地方気象台と連携及び協力に関する協定を締結。 |
| 2019年2月 | 大分県と災害対策の連携に関する協定を締結。 |
| 2019年5月 | 国土交通省国土地理院九州地方測量部と連携及び協力に関する協定を締結。 |
| 2020年7月 | 令和2年7月豪雨 ・大分県からの要請により大分県災害対策本部及び日田市での災害対応支援 ・国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所からの要請によりセンター教職員(TEC-DOCTOR)を災害派遣 ・被災した日田市,九重町に災害ボランティアを派遣 |
| 2021年7月 | センター次長(主担当教員)の鶴成 悦久が教授に昇任。クロスアポイントメント制度に関する協定により,減災・復興デザイン教育研究部門に山本 竜伸准教授を配置。 |
| 2022年4月 | 山本 健太郎 准教授(地盤工学)が主担当教員として着任。 |
| 2022年8月 | 石井 圭亮 准教授(救急災害医療)が主担当教員として着任。 |
| 2022年9月 | 台風第14号により被災した由布市に災害ボランティアを派遣 |
| 2022年10月 | センター長に鶴成 悦久 教授が就任。 |
| 2022年11月 | センター次長に下村 剛(医学部附属病院医療情報部・教授)が就任。 |
| 2023年3月 | 別府市と鶴見岳・伽藍岳の火山防災に係る連携協定を締結。 |
| 2023年4月 | 岩佐 佳哉 助教(自然地理学)が主担当教員として着任。 |
| 2023年5月 | 三﨑 貴弘 講師(河川工学・河川環境工学)が主担当教員として着任。 |
| 2024年4月 | 福田 昌代 助教(ランドスケープ科学,都市計画,地域研究)が主担当教員として着任。 |
| 2025年4月 | 後藤 恒爾 が防災コーディネーターとして着任。 |
設置の目的
センターでは大分県における防災・減災の実現を目指して,以下の課題に対して,各学部・センターや学外組織(国,自治体等)・関連主体との連携を図りながら取り組み,安全・安心社会構築へ資することを目的とします。
①分野横断型の教育・研究を行い,安全・安心社会構築に寄与する人材・技術者の養成
②地域防災力向上のための防災教育と活動の支援
③救援救護や災害調査を柱とした学内外との連携による災害支援・災害調査および効率的な情報・データの共有化
④災害後の復旧・復興支援を支える平時からの地域活性化と復興デザインの取組
⑤その他,地域の防災力向上に寄与しうる取組
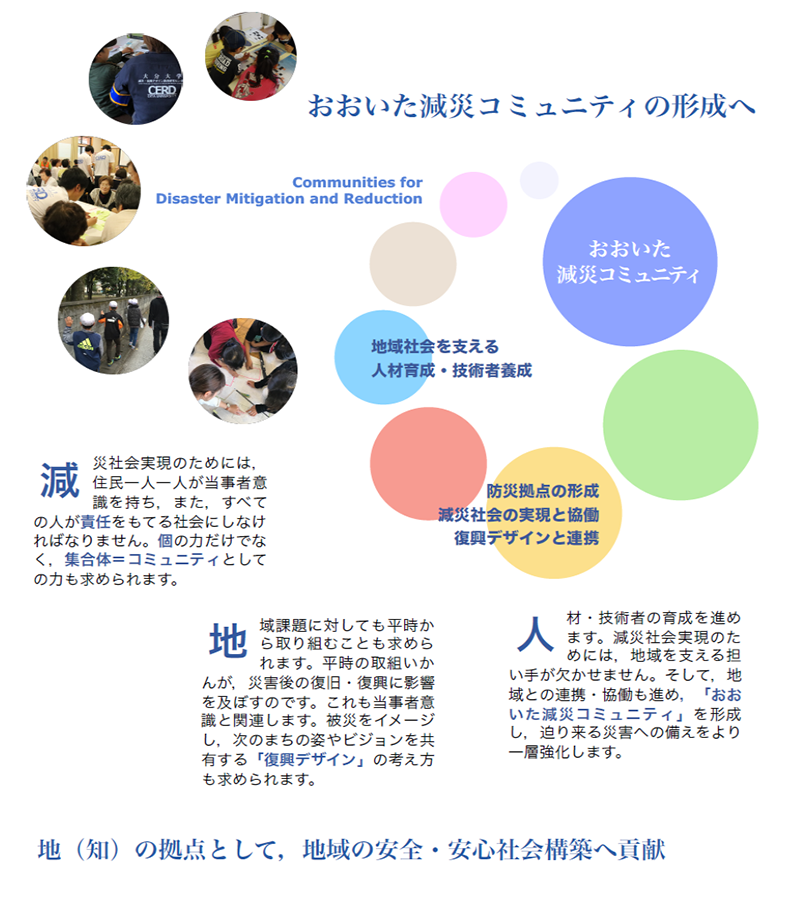
プロジェクトの内容
センターは,以下の「調査研究」(救援救護(災害医療)との連携),「防災教育」,「復興デザイン」の各プロジェクトに取り組みます。
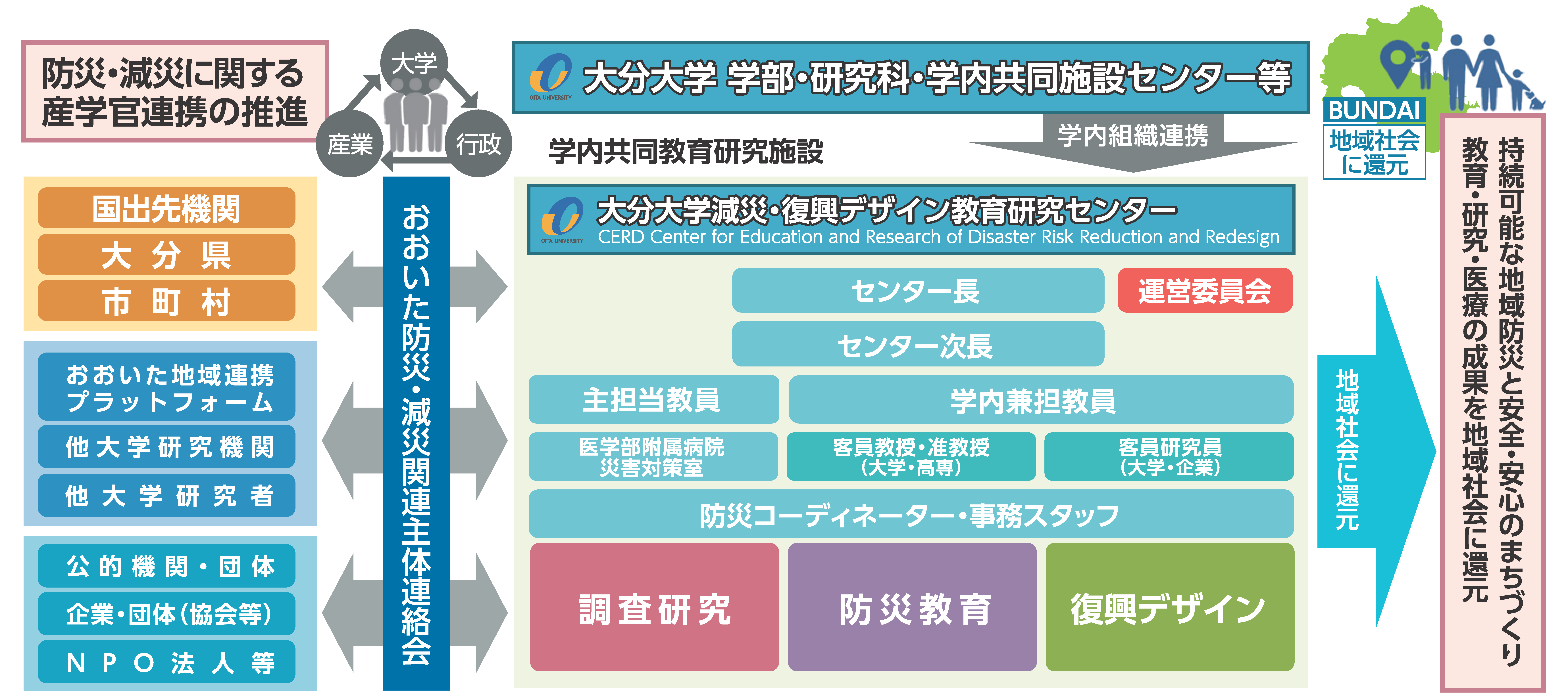
- ①調査研究
- ドローンなどの最新技術を活用し,災害情報を迅速かつ機動的に調査・収集し,メカニズムの解明や災害対応のための情報共有・提供,技術的な支援を行います。また,医学部附属病院災害対策室との連携も図ります。
【救援救護・災害支援との連携】
医学部附属病院災害対策室と連携し,災害情報の共有を図ります。 - ②防災教育
- 地域・学校における防災教育や活動の支援,地域防災イベントを実施します。また,学内においては,教養教育科目「防災学」等の開講,ボランティア教育等により,地域防災に資する人材育成のための教育の充実も図ります。
- ③復興デザイン
- 平時には地域づくりや地域分析,そして災害後の都市・地域のビジョンを共有するための取組となる「復興デザイン(事前復興)」を進めます。また,災害後の文化財復旧支援,学生ボランティア派遣支援も学内外の組織と連携しながら実施します。
センタースタッフ
| センター長 | 教授 鶴成 悦久(減災科学,海岸環境工学,空間情報工学,災害情報学) クライシスマネジメント機構副機構長 |
|---|---|
| センター次長 | 教授 下村 剛(医学部附属病院医療情報部長・災害医療) 医学部附属病院災害マネジメント総合支援センター長 |
| センター主担当教員 | 准教授 山本 健太郎(地盤工学) |
| センター主担当教員 | 准教授 山本 竜伸(情報工学)クロスアポイントメント制度 CERD大学発ベンチャー(株)INSPIRATION PLUS 代表取締役 |
| センター主担当教員 | 講師 三﨑 貴弘(河川工学・河川環境工学) |
| センター主担当教員 | 助教 福田 昌代(ランドスケープ科学,都市計画) |
| センター主担当教員 | 公募中 |
| 防災コーディネーター | 後藤 恒爾 |
| 事務所掌 | 研究推進部産学連携課,コーディネーター(事務担当) 杉田 智美 |
| 事務補佐員 | 佐藤 一征,樋口 美也子,山岡 明美 |
| 研究室配属 | 鷲見 孝明(D2),福田 和純(D2),青野 仰輝(B3),松尾 海杜(B3) |
| 学生CERD | 代 表:矢奥 晴久(福祉健康科学部),副代表:佐藤 凜 (理工学部),部員80名 |
※2025.4現在
センター兼担教員
| 氏 名 | 所属 | 専門 |
|---|---|---|
| 川田 菜穂子 | 教育学部・教授 | 住居学・住宅政策,住宅問題,住宅計画 |
| 本谷 るり | 経済学部・教授 | 経営組織論,経営戦略論 |
| 大井 尚司 | 経済学部・教授 | 交通経済学,交通政策,地域交通計画,観光,公益事業論,公企業論,物流論 |
| 山浦 陽一 | 経済学部・准教授 | 農業経済学 |
| 花田 克浩 | 医学部・講師 | 生物物理学,食品科学 |
| 佐藤 弘樹 | 医学部・講師 | 救急医学, 医療管理学,医療系社会学 |
| 奥山 みなみ | 医学部・講師 | 獣医学,野生動物学 |
| 田上 公俊 | 理工学部・教授 | 熱工学, 燃焼工学 |
| 菊池 武士 | 理工学部・教授 | ロボット工学,動作支援技術 |
| 衣本 太郎 | 理工学部・教授 | 機能物質化学,電気化学 |
| 黒木 正幸 | 理工学部・教授 | 建築構造学 |
| 富来 礼次 | 理工学部・教授 | 建築環境工学,建築音響学 |
| 田中 圭 | 理工学部・准教授 | 建築構造学,木質構造学 |
| 徳丸 治 | 福祉健康科学部・教授 | 生理学,航空宇宙医学,小児科学 |
| 渡辺 亘 | 福祉健康科学部・教授 | 臨床心理学 |
| 西口 宏泰 | 研究マネジメント機構・准教授 | 触媒,光化学,機器分析 |
| 小川 領一 | 研究マネジメント機構・准教授 | 開発学,廃棄物管理 |
客員教授・客員准教授(学外)
| 氏 名 | 所属 |
|---|---|
| 客員教授 大沢 信二 | 京都大学・教授(理学研究科 附属地球熱学研究施設) |
| 客員教授 三谷 泰浩 | 九州大学・教授(工学研究院 附属アジア防災研究センター) |
| 客員教授 西 隆一郎 | 鹿児島大学・教授 |
| 客員教授 江島 伸興 | 大分大学医学部・名誉教授 |
| 客員教授 金子 聰 | 長崎大学・教授(熱帯医学研究所) |
| 客員教授 新地 浩一 | 佐賀大学・名誉教授(医学部社会医学講座) |
| 客員教授 平岡 透 | 長崎県立大学・教授 |
| 客員教授 山崎 栄一 | 関西大学・教授 |
| 客員教授 小西 忠司 | 大分工業高等専門学校・名誉教授、NPO 法人あなたのくうかんおおいた |
| 客員教授 前 稔文 | 大分工業高等専門学校・教授 |
| 客員教授 細谷 和範 | 津山工業高等専門学校・教授 |
| 客員教授 加來 浩器 | 防衛医科大学校・教授(防衛医学研究センター) |
| 客員教授 松木 泰憲 | 桜十字八代リハビリテーション病院 |
| 客員教授 石井 圭亮 | 健裕会永冨脳神経外科病院 |
| 客員教授 岡本 文雄 | 元大分県生活環境部防災局長 |
| 客員教授 板井 幸則 | 元臼杵市消防本部消防長(元減災・復興デザイン教育研究センター防災コーディネーター) |
| 客員准教授 石黒 聡士 | 愛媛大学・准教授 |
| 客員准教授 廣田 雅春 | 岡山理科大学・准教授 |
客員研究員(学外)
| 氏 名 | 所属 |
|---|---|
| 岩佐 佳哉 | 福岡教育大学・講師(元減災・復興デザイン教育研究センター主担当教員) |
| 大島 郁夫 | (株)アストソイル |
| 大塚 哲哉 | 九州建設コンサルタント(株) |
| 川原 太郎 | (株)日建コンサルタント |
| 橋本 哲男 | (株)日建コンサルタント |
| 田尻 雅彦 | 大分合同新聞社 |
| 藤内 教史 | 大分合同新聞社 |
| 中濃 耕司 | (株)久栄綜合コンサルタント:福岡県 |
| 吉田 彰 | SAPジャパン(株):東京都 |
| 臼杵 伸浩 | アジア航測(株):東京都 |
| 佐野 寿聰 | アジア航測(株):東京都 |
| 牧 澄枝 | アジア航測(株):東京都 |
| 荒井 健一 | アジア航測(株):東京都 |
| 大野 桃菜 | アジア航測(株):東京都 |
| 財津 宏一 | 日本放送協会:東京都 |
| 黒田 真吾 | 一席:東京都 |
| 佐藤 大樹 | (株)ザイナス |
| 大西 徹 | 元気象庁福岡管区気象台 |
防災・減災に関する連携・協定
国または地方公共団体
- 国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所(2018.4.5 締結)
- http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/
- 国土交通省 気象庁 大分地方気象台(2018.11.12 締結)
- https://www.data.jma.go.jp/oita/
- 国土交通省 国土地理院 九州地方測量部(2019.5.20 締結)
- https://www.gsi.go.jp/kyusyu/
- 大分県(2019.2.4 締結)
- http://www.pref.oita.jp/
- 大分市(2017.3.5 締結)
- http://www.city.oita.oita.jp/
- 佐伯市(2018.4.16 締結)
- http://www.city.saiki.oita.jp/
- 別府市(2023.3.24 締結)
- https://www.city.beppu.oita.jp/
- 由布市(2025.2.12 締結)
- https://www.city.yufu.oita.jp/
公的機関及び大学
- 九州大学大学院 工学研究院附属アジア防災研究センター(2018.11.1 締結)
- http://asia.doc.kyushu-u.ac.jp/
企業・団体等
- 大分合同新聞(2015.1.16 締結)
- http://www.oita-press.co.jp/
- OBS大分放送(2018.8.7 締結)
- https://obs-oita.co.jp/
- NPO法人 おおいた環境保全フォーラム(相互協力)
- https://oita-ecf.com/
- NPO法人 大分県防災活動支援センター(相互協力)
- http://opdo.sakura.ne.jp/
- NPO法人 リエラ(相互協力)
- https://www.re-area-hita.com/