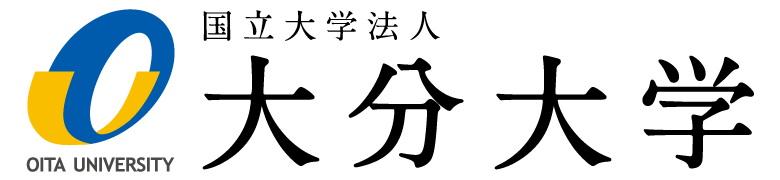-
【報告】減災シンポジウムin中津開催について
2020年2月2日(日)
令和2年1月26日(日)に中津市文化会館において,大分大学主催(共催に中津市,大分県,国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所,気象庁大分地方気象台)による「減災シンポジウムin中津」を開催しました。当日は休日にもかかわらずに市内外から500名を超える方が訪れ,災害多発時代を迎えた現代社会において,地域防災や減災とは何かを考えるシンポジウムとなりました。 シンポジウム冒頭では大分大学減災・復興デザイン教育研究センター次長の鶴成悦久准教授による「中津市の災害を知る」をテーマに,地球温暖化に伴う気候変動によって災害が世界的に頻発する現代,そして少子高齢化と人口減少が進む地域の現実,さらには中津市内全域のリスクなど災害多発時代を迎えた現代社会に対し,過去・現在・未来を見据えた減災社会の構築について報告しました。 高校生と大学生らの発表では令和元年11月16日に開催した「フィールドツアー」について報告。そして大学の研究紹介や高校でNGOの活動に参加した外園さんがネパールの現状について報告しました。最後に中津市による過去の災害と現在の防災対応,そして未来を見据えた「バックキャスティング」によるワークショップ(WSの様子はhttps://youtu.be/6cI0kamhD5Iにて公開しています)はを令和元年12月26日に開催し,IoTそしてAI時代を迎えるためにITを用いた施策や人材育成等について提案しました。最後に,これらの結果から導かれた若者による「中津市への提言」をまとめ発表しました。 市民参加型デスカッションにおいては,パネラーとして中津市長 奥塚 正典 様,大分県生活環境部防災局防災危機管理監 福岡 弘毅 様,国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所長 鹿毛 英樹 様,気象庁大分地方気象台長 北﨑 康文 様,中津市民代表 中津市防災士協議会長 稗田二郎 様,中津北高等学校2年 外園寛樹 様に,コメンテーターとして九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター 三谷 泰浩 教授(減災センター客員教授),コーディネーターに減災センター鶴成次長によって「災害多発時代を生きるために」をテーマに討議が進みました。討議では来場者にクリッカーと呼ばれる装置がランダムに配布され,スクリーンに映し出されるアンケートに回答し,結果からどのような対応が必要なのか,また防災行政としてどのように対応すべきなのかといった議論が進み,会場と一体化したパネルディスカッションが開催されました。 大分大学では地域貢献の一環として毎年,地方公共団体と協働による「減災シンポジウム」(令和元年より「防災」シンポジウムから変更しております)を開催しています。令和2年度の開催地が決まりましたらHPで報告いたします。 会場の様子 若者からの中津市への提言 1. それぞれであらかじめ備蓄,逃げる準備をする 2. 災害の予知,予測をあらかじめしておく 3. 災害遺構を残すだけでなく,継承していく 4. 小中学校における防災教育の拡充が必要 減災シンポジウムin中津 フィールドツアー動画 [embed]https://youtu.be/IS6b5Jxyh80[/embed] [embed]https://youtu.be/6cI0kamhD5I[/embed] クリッカーを用いたアンケート結果 クリッカーは当日参加者にランダムに配布し220名の方から回答がありました。 会場で表示したアンケート結果についてはこちらをご覧ください
-
令和元年度フィールドツアー等のYoutube公開動画について
2020年2月1日(土)
減災センターでは令和元年度に実施したフィールドツアー関連の動画について公開しています。 「火山防災シンポジウム」 地域のリスクを知り,多様な災害に備える 日時 2019年11月24日(日) 13:30 ▷ 16:30(開場 13:00) 会場 別府ビーコンプラザ 国際会議室 [embed]https://youtu.be/tXFEaPWLy_E[/embed] [embed]https://youtu.be/Hm9QN9g_Ye8[/embed] [embed]https://youtu.be/n4bY2J8GrgA[/embed] 4K 360°カメラで撮影しておりYoutube及び360°カメラ対応TVに対応しています。 減災シンポジウムin中津 -災害多発時代を生きるために- 日時 令和2年1月26日(日) 13:30 ▷ 16:30(開場 13:00) 場所 中津市文化会館 [embed]https://youtu.be/IS6b5Jxyh80[/embed] [embed]https://youtu.be/6cI0kamhD5I[/embed]
-
「大分県災害データアーカイブ」リニューアルについて
2020年1月15日(水)
令和2年1月15日よりNHK大分放送局と大分大学減災・復興デザイン教育研究センターが共同で「大分県災害データアーカイブ」の制作・運用を開始しました。 「大分県災害データアーカイブ」はおよそ1300年間に発生した災害の記録を地図上に表示しているほか,当時の気象情報やNHK大分放送局が公開する映像を閲覧することができます。 今回,共同制作・運用に際して「大分県災害データアーカイブ」のリニューアルを行い,「災害伝承碑」をはじめとした災害種の拡充及び小分類化を図りました。 減災センターではNHK大分放送局と「大分県災害データアーカイブ」の共同制作・運用を進めるほか,関係機関や地域の方々とともに災害記録の構築や利用促進に向けた取組みを進めます。 NHK大分放送局「大分県災害データアーカイブ」ポータルサイト https://www.nhk.or.jp/oita/saigai-data/ 大分大学減災センター「大分県災害データアーカイブ」 http://www.cerd.oita-u.ac.jp/saigai-data-archive/
-
河川防災・減災セミナー2020(1/17開催)
2019年12月12日(木)
大分川・大野川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会(下流部)と大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの主催による「河川防災・減災セミナー2020」を以下の通り開催します。 近年,豪雨に伴う激甚災害が頻発しています。平成30年7月豪雨や令和元年台風第19号では,多数の給油取扱所の浸水,浸水による漏電火災やアルミニウム工場による爆発等が発生。令和元年8月の前線に伴う大雨による浸水では,佐賀県の鉄工所において多量の油が流出する事故が発生しました。 これらの災害に対しては,地域の洪水ハザードマップを参考にリスクを確認し,災害時における行動や対策を平時からあらかじめ備えておくことが重要です。 本セミナーは,事業所を対象に,洪水に備えて事前対策や事業計画を作成するために必要な知識の習得を目的として,大分川と大野川の洪水リスクや浸水に備えた先進的な事業所の取り組み事例等を紹介します。 河川防災・減災セミナー2020 日 時:令和2年1月17日(金)13時30分~16時10分(予定) 場 所:J:COMホルトホール大分 市民ホール(大ホール) 参加費:無料 申込み:不要 ※会場に直接お越しください 詳しくは資料(PDF)をご覧ください。
-
減災シンポジウムin中津 ―災害多発時代を生きるために―(1/26開催)
2019年12月12日(木)
大分大学では,平成23年度から県内各地で地域における防災・減災を目指す「防災シンポジウム」(今年度より「減災シンポジウム」)を開催しています。これは県民の防災意識の向上と自治体等の防災・減災対策の一助とするため,本学と自治体とが協働で開催しています。 令和元年度については平成24年・平成29年九州北部豪雨や平成30年4月耶馬渓町金吉山崩れにより大きな災害が発生した中津市において「減災シンポジウムin中津―災害多発時代を生きるために―」を開催します。す。なお,事前に中津市の高校生と本学学生らによる中津市内を対象としたフィールドツアーを11/16(土)に開催しています。このツアーでは中津市内の山間部から中心地にかけて過去の災害地や想定される災害などを調べ,減災社会に向けた未来の地域づくりを生徒や学生らが検討しました。これらの結果をふまえ,次世代を担う若者から中津市への提言として本シンポジウムで発表します。 減災シンポジウムin中津 -災害多発時代を生きるために-(PDF) 日 時:令和2年1月26日(日) 13:30-16:30 場 所:中津市文化会館 主 催:国立大学法人 大分大学 共 催:国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所,気象庁大分地方気象台,大分県,中津市 後 援:九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター,国土地理院九州地方測量部,BUILD OITA〈おおいた建設人材共育ネットワーク〉,大分合同新聞社 協 力:地理空間情報活用に関する大分地区産学官連携検討会,特定非営利活動法人リエラ 申込み:不要 ※直接会場にお越しください (1) 中津市の災害を知る 講師:大分大学減災・復興デザイン教育研究センター次長 准教授 鶴成 悦久) (2) 高校生・大学生による減災社会への提言(大学生・高校生) (3) 「災害多発時代を生きるために」市民参加型パネルディスカッション <パネリスト> 中津市長 奥塚 正典 中津市民 市民代表者 大分県立中津北高等学校 高校生代表者 大分県生活環境部防災局防災危機管理監 福岡 弘毅 国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所長 鹿毛 英樹 気象庁大分地方気象台 北﨑 康文 <コメンテーター> 九州大学工学研究院附属アジア防災研究センター教授 三谷 泰浩 (大分大学減災・復興デザイン教育研究センター客員教授) <コーディネーター> 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター次長 准教授 鶴成 悦久 <司会> 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター長 教授 小林 祐司
-
Geoアクティビティコンテストにおいて地域貢献賞を受賞!
2019年12月11日(水)
大分大学トピックスより https://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/topics/2019-063.html 11月28日~30日に日本科学未来館(東京都江東区)において開催されたGeoアクティビティコンテストにおいて本学学生が発表を行い,地域貢献賞を受賞しました。 Geoアクティビティコンテストとは,国土交通省国土地理院が主催し,地理空間情報の利活用に関する様々な「取組」「アイディア」「サービス」などを展示・発表で紹介し,参加者や来場者との交流を通じて,優良事例の育成・普及,新しいサービスの創出など地理空間情報の活用促進を目的としたイベントです。 本学からは減災・復興デザイン教育研究センター(以下,減災センター)として出展し,火山模型の展示や防災教育のコンテンツの紹介を行い,これまで減災センターが取り組んできたGISを活用した防災教育や火山防災に関する事例を発表しました。発表を行った工学研究科の江内谷万緒さんと大野桃菜さんには,地理空間情報の活用推進に寄与する優秀なものと認められ,地域貢献賞が授与されました。 【地域貢献賞 受賞】 テーマ:GISを活用した防災教育・コンテンツ制作と学生からの情報発信」 発表者:大学院工学研究科 江内谷万緒さん・大野桃菜さん
-
「火山防災シンポジウム」を開催します(11月24日・日曜日)
2019年11月14日(木)
本年1月に開催した火山防災セミナーに引き続き,今年度も「火山防災シンポジウム」を開催します。詳細は以下をご覧下さい。申込不要,先着200名となっています。 フライヤー → PDF お問い合わせは大分大学減災・復興デザイン教育研究センターまで。 Mail : cerd-office@@@oita-u.ac.jp ※@を一つにして下さい。 Phone : 097-554-7333 「火山防災シンポジウム」 地域のリスクを知り,多様な災害に備える 日時 2019年11月24日(日) 13:30 ▷ 16:30(開場 13:00) 会場 別府ビーコンプラザ 国際会議室 1.開催趣旨 多様化,激甚化する今日の災害。全国的にも自然災害が多発している状況がある。ここ大分県は,地震,津波,土砂災害,洪水,火山など多様な自然災害のリスクを有している地域である。シンポジウム開催地の別府市においては,これまでも密集市街地において火災が多く発生しており,自然災害だけでなく都市災害のリスクも有している。観光地として全国,世界に名をはせる別府市においては,温泉資源そのものは自然の恵みによるものであることは言うまでもなく,自然と共生する視点はこれからも欠かすことはできない。多様な災害を想定しながら,「被災をした後のまちづくりをどう進めるのか」は今日我々に突きつけられた課題でもある。本年1月には「火山防災セミナー」を開催し,火山防災上の課題共有を図ったところである。しかし,「火山」だけの切り口では災害をイメージすることは難しく,日常的な生活やまちづくり,都市政策と連携をさせながら,「何をすべきか」を考える必要がある。このような観点のもとで,雲仙普賢岳での災害から,ここ大分県においても火山災害を想定した対応のあり方やまちづくりに求められること,さらには地域防災のあり方を考える機会を提供し,共に考えたい。 2.プログラム 13:00 開場 13:30 開会挨拶等 13:35 基調講演「雲仙普賢岳火山災害から学ぶ」 三陸ジオパーク推進協議会上席推進員・内閣府火山防災エキスパート 杉本 伸一 氏 14:30 学生発表「地域防災に求められること 〜まちのあり方,災害への向き合い方〜」 大分大学 押江悠美(工学研究科),瀬井亮太(理工学部) 別府大学 根之木誉主,前畑奈央(国際経営学部国際経営学科) 15:00 休憩 15:10 ディスカッション※クリッカーを活用した会場との意見交換も実施 ▼パネリスト 別府市長 長野 恭紘 氏 基調講演講師 杉本 伸一 氏 京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設長・教授 大沢 信二 氏 ▼コーディネーター 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター センター長 小林 祐司 16:30 終了
-
大分大学開放イベントに出展しました。
2019年11月6日(水)
11月4日(祝・月)に行われた大分大学開放イベントに「防災・減災に役に立つドローン技術と土のうづくり講座」をテーマとして出展しました。 当日、災害調査などで使用する小型ドローンの展示や小林研究室の学生たちの協力のもと出展ブースを訪れた方々にドローンのフライトシミュレータや事前に撮影したドローンから見える景色をVRゴーグルを使って体感していただきました。 また、板井防災コーディネーターによる土のう袋の作り方やその積み方を同時開催し、使用する時の土のう袋の重さがどれくらいになるのか体感してもらい、実践講座として土のう袋のくくり方・積み方を体験していただきました。 事前に準備した持ち運びが軽い土のう袋に取り替えて、何気なく使う土のう袋のくくり方、くくった土のう袋を実際にどのように積むのか展示ブースを訪れた方々に実際に積んで体験してもらいました。 ドローンを間近で体験できる、土のう袋を実際に積んだりする体験という事もあり、多くの方が減災・復興デザイン教育研究センターの展示ブースまで足を運んでいただきまして誠にありがとうございました。 この機会をきっかけに防災・減災についてご家族などでお話しをするきっかけ作りになればと思っております。 開放イベント展示ブースの様子 ドローンシミュレータやVRゴーグルを使っての模擬体験 土のう作り講座にて、実際に使うときの土のう袋の重さを体験
-
News Letter vol.3 ( Oct., 2019)を公開しました
2019年11月5日(火)
News Letter vol.3を公開しました。 今回の特集は「大分県災害データアーカイブについて」です。大分県内外にてボランティア活動をされている尾畠春夫さんを招いての災害ボランティア講習会などの報告も掲載しています。 メニュー「刊行物」→「News Letter」 News Letter vol.3(Oct., 2019) PDF
-
「減災シンポジウムin中津 フィールドツアー」学生参加者募集
2019年10月8日(火)
令和2年1月26日(日)に中津市で開催される減災シンポジウムに合わせ,地元高校生と大学生らによる中津市内を対象としたフィールドツアーを開催します。 詳しくは以下の募集内容をご確認のうえ,以下の申込フォームにて応募ください。参加費無料(弁当代含む) 申込フォーム 以下の申込フォームにて氏名・所属学部学科・学年・電話番号・メールを記入し,お申し込みください。https://forms.gle/s7r6uSwoGGjSHzCQ8 申込期限 10月23日(水)まで 過去の災害地や想定される災害を学ぶフィールドツアー 令和元年度 減災シンポジウムin中津-災害多発時代を生きるために- 日 時:令和元年11月16日 (土) 9時00分~16時00分(中津北高校発着時間) 場 所:中津市内(中津市内及び三光,本耶馬渓町,耶馬渓町) 主 催:国立大学法人大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター 共 催:中津市 (目 的) 近年,日本全国で自然災害が多発化し,その被害においても激甚化・多様化しています。 これら自然多発時代を生きるために,次世代を担う若者世代に対し,過去の災害を学び,そして災害想定区域における多様な災害への備えや課題ついて考え,検証し,地域社会に発信することは,これからの地域防災を強化するうえで重要です。 そこで令和2年1月26日(日)に中津市で開催される減災シンポジウムに合わせ,地元高校生と大学生らによる中津市内を対象としたフィールドツアーを開催いたします。このツアーでは中津市内の山間部から中心地にかけて過去の災害地や想定される災害などを調べ,減災社会に向けた未来の地域づくりを生徒や学生らが検討いたします。 フィールドツアー主な個所 ①無降雨時災害②山国川における豪雨災害(平成24年・平成29年九州北部豪雨)③データアーカイブ-過去の災害からの教訓(昭和6年7月 八面山溜池の決壊)④中津市中心地における災害想定(周防灘断層・南海トラフ・洪水・浸水想定) 参加者(フィールドワーク) 〇大分大学学生 20名程度(学部問わず) 〇中津北高校生 10名程度(1・2年生) 〇その他,関係者 スケジュール 11月16日(土) ※予定は変更することもあります。7:30 大分大学 出発 9:00 中津北高校 10:00 耶馬溪公民館 ① 無降雨時災害 11:00 出 発 11:30 青の洞門周辺 ②山国川における豪雨災害 昼食 13:00 出発 13:40 三光地区上田口公民館 ③データアーカイブ過去の災害からの教訓 14:40 出発 15:10 中津市内 ④中津市中心地における災害想定 16:00 中津北高校 17:30 大分大学 着