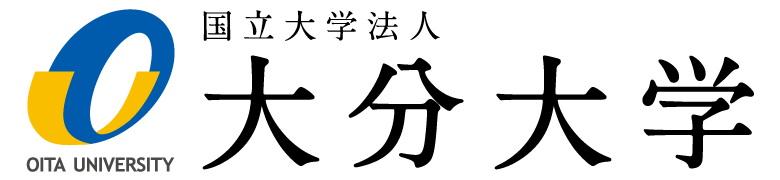-
平成30年7月豪雨について
2018年7月9日(月)
平成30年7月5日から8日にかけて西日本を中心に記録的な豪雨が発生し,各地で甚大な被害となりました。 この豪雨災害により,各地で多くの方が被災され,現在でも行方不明者の捜索等,人命救助活動が行われておます。 このたびの豪雨災害によって, お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに,ご遺族に心からお悔み申し上げます。そして,被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 被災地の一日も早い復旧・復興を心より願っております。
-
防災を身近に感じて頂くための「防災講座」について
2018年6月23日(土)
減災・復興デザイン教育研究センターでは,地域の皆様に「防災を身近に感じて頂くため」の防災講座を行っています。 講座の第一号となった6月22日(金)は,臼杵市より約20名が減災センターに訪れ防災講座を受講しました。講座では板井防災コーディネーターが講師を務め,馬渓町金吉での山崩れや大阪での地震について講話を行いました。講座終了後は,学生交流会館B-Forêt(学生食堂)にて昼食をとられました。本学に初めて来られる方も多く,初めての大学の敷地の広さに驚いてた様子でした。短い間でしたが,参加した方の多くは身近な防災・減災への意識を再度,認識されたと思います。 減災センターでは,地域の要望に応じて,防災講座(無償)を定期的に開催しています。 地域だけではなく小中学校,高校などでも出前講座を行っておりますので,お気軽にご相談ください。 防災講座については↓こちらをご覧ください。 http://www.cerd.oita-u.ac.jp/wa/wp-content/uploads/2018/05/bousai_p.pdf 防災講座の様子(産学官連携推進機構2Fセミナー室) 講師を務める板井防災コーディネーター(元臼杵市消防長) 大分大学キャンパスの案内 学生交流会館B-Forêt(学生食堂)
-
【公募情報】事務補佐員1名募集について
2018年6月19日(火)
減災センターでは組織能力の向上を図るため,事務スタッフを公募しています。 詳細につきましては,以下の募集要項ページを御確認ください。 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター(CERD) 事務補佐員 1名 ・採用予定日:平成30年8月1日 ・募集期限:平成30年6月29日(金)※必着 <募集要項> http://www.oita-u.ac.jp/000042074.pdf <お問い合わせ・書類提出先> 大分大学 研究・社会連携課 社会連携係 担当:藤澤 〒870-1192 大分市大字旦野原700番地 TEL:097-554-8533 E-mail:tirenアットマークoita-u.ac.jp
-
日田市小野公民館でワークショップを実施
2018年6月16日(土)
本日減災・復興デザイン教育研究センター(CERD)は,昨年度の九州北部豪雨において大規模な被害が発生した日田市小野地区において,ワークショップを実施しました。 現在,地域では災害時の対応のあり方,これからの地域をどうすべきかといった課題を抱えており,小野公民館の依頼を受け,今回のワークショップを開催することとなりました。 (今回のワークショップは,8月に日田市内で開催予定の防災シンポジウムの事前調査も兼ねています。) 地域からは(想定以上の)100名を超える多くの住民の方々に参加を頂きました。 大分大学からは減災・復興デザイン教育研究センターの教職員4名(小林,鶴成,板井CD,杉田AS),小林祐司都市計画研究室(理工・建築)の大学院生・学部生12名が参加しました。 1.10:00-10:30 災害対応のあり方,質問への回答(小林,鶴成) ここでは,センターの小林と鶴成が「昨年度の災害の状況(気象状況も含めて)」,「災害のメカニズム」などを解説し,さらに事前に公民館から頂いていた質問への回答を行いました。 (昨年度当センターが撮影したUAVによる空撮映像なども見て頂きました。) そして強調させて頂いたのは,「このような課題の結論を見いだすことの困難さ」。だからこそ,「皆さんがどういう想いなのか。どう考えているのかを共有する機会が必要」ではないかということです。1回で終わらせるのではなく,何度も粘り強く議論を重ねていくべきだと訴えました。 冒頭の挨拶,講演 2.10:30 - 11:50 ワークショップ ワークショップでは以下の流れで,「住むということ」「災害時対応」の二つの考え方について整理を行いました。 A:フリートーク B:アイデア出し (1)この地域に住むために必要なことや対策とは? (2)災害時対応をどうするか?(人的被害を出さないためにどうすべきか?) C:アイデアの共有+整理 人数が想定よりも多かったため,各班を担当する学生さんも大変な作業となりました。 以下WSの様子 3.11:50 - 12:00 まとめ 出された意見や事前に想定した内容から,住むことに対する課題(地域課題)や災害時対応のコミュニティのあり方,早期避難の必要性などを指摘しました。さらに,防災教育,自然に目を向け変化を捉えて共有すること,また子育て世代の積極的な関与を進めること,学校現場との連携などの重要性,そして「当事者意識を持つこと」「災害対応,防災対策は一人一人に責任がある」ことも加えて述べさせて頂きました。 今回の意見を精査し,次のWSで共有することと次の議論へ繋げることをお約束し,ワークショップを終了しました。 災害から一年を経ての当センターの関与ということになりましたが,今後も地域の依頼に応えていきます。また,学校との連携なども視野に,子ども達の安全性の確保をいかに実現するかなども議論,提案を進めていきたいと考えています。 終了後は,災害発生現場の視察を行いました。
-
2018年度 地理科学学会春季学術大会にて発表を行いました
2018年6月5日(火)
センター兼担教員である教育学部の小山が,2018年6月2日に広島大学で開催された『2018年度 地理科学学会春季学術大会』にて,以下のタイトルで発表を行いました。 小山拓志・土居晴洋・古賀精治(大分大学教育学部):地域の災害リスクを踏まえた特別支援学校における防災教育の実践と教職員の防災・減災意識の現状 本発表は,2018年3月20日に教育学部主催(共催:CERD,福祉科学研究センター,大分県教育委員会)で開催された,地理学×特支×防災教育シンポジウム「地域の災害リスクを踏まえた特別支援学校における防災教育を考える」で公表した成果をまとめたものです。
-
「火山防災を考える」島原市フィールドツアーの開催
2018年5月21日(月)
5月17日(木)・18(金)に長崎県島原市にて大分大学の学生(学部・大学院生)を対象とした「火山防災を考える」島原市フィールドツアーを,アジア航測株式会社(東京都)の協力により実施しました。 ※ツアーの詳細についてはhttp://www.cerd.oita-u.ac.jp/2018/04/10/tour2018_unzen/ 島原市フィールドツアーでは雲仙普賢岳の火山災害と復興事例を通じ,火山災害における復興デザインを学生の目線から学び・考えることを目的に実施しました。17日は雲仙災害記念館をはじめとし,仁田団地第一公園から眉山崩壊の流山の地形を見学。翌日18日には平成新山ネイチャーセンターや旧大野木場小学校被災校舎を見学。途中,アジア航測の社会インフラマネジメント副事業部長の臼杵様,西日本企画室長の牧様より,雲仙普賢岳の火山災害の解説や復興事業について詳細な説明会も行われました。 両日とも天候が悪く,雲仙普賢岳を見ることができませんでしたが,雲仙普賢岳の噴火による火山災害発生から27年経った今でも,火山災害の恐ろしさを実感することができました。さらに,火山とともに生きる島原市と災害からの復興を遂げた「まち」の歴史を感じ,復興デザインの重要性について学生らは理解を深めました。 大分県でも身近な火山に鶴見岳・伽藍岳,由布岳,そして九重山があり,一部の地域では雲仙普賢岳と同様のリスクを抱えています。雲仙普賢岳の火山災害から復興デザインを学び,復旧・復興までのプロセス,そして共有すべきもの。すなわち「復興」とは何か?をテーマに,フィールドツアーは今後大分県内にて実施する予定です。 「火山防災を考える」については,復興デザインの新たな研究テーマとしてスタートすることと同時に,大分県における「火山防災」について改めて地域と共に再考できるよう,減災センターでは諸活動を展開していきます。
-
大分大学災害ボランティア講習会(学内向け)
2018年5月2日(水)
近年,東日本大震災をはじめ,平成28年4月に発生した熊本・大分地震による大規模災害。そして,平成29年九州北部豪雨災害や台風18号災害によって,多発する豪雨災害に対し,復旧・復興に係るボランティアの協力が大分県内でも重要視されるようになりました。大分大学でも平成29年度に発災した災害に対して,学生・教職員の多くが災害ボランティアとして参加しました。今後,大分県内で頻発する災害に対して,復旧・復興へのボランティア活動に,学生としてどのように関わっていくのか,そして災害ボランティアとは何かを事前に学ぶことで,被災地で行うボランティア活動に迅速に対応し,機能的な対応が期待されます。 そこで,災害ボランティアに参加を希望する学生に対して,事前に災害ボランティアの本質を伝え,被災地における復興・復旧活動への理解を進めるための講習会を開催いたします。 実際に被災地へ災害ボランティアとして参加・活動する場合は,本講習の受講が必須条件となります。 主催:学生支援課,減災・復興デザイン教育研究センター(CERD) 日時:平成30年5月29日(火) 16:30-17:30 場所:大分大学旦野原キャンパス教養教育棟第2大講義室 講師:ひちくボランティアセンター[日田市大鶴地区] 日田市地域おこし協力隊 松永 鎌矢 様(大分大学OB) CERD防災コーディネーター 板井 幸則 様(元臼杵市消防長) その他,大分県で発生した災害の情報,学生ボランティア体験談等 特典:受講修了者には「災害ボランティア講習会受講修了証」を発行し,活動に参加した場合は[災害ボランティア協力隊]の認定を行います。 申込:[氏名][ふりがな][学部・学科・コース・学年]を以下のアドレスに送信 学生支援課(今村)seisiesiアットマークoita-u.ac.jp 締切は5/25(金)まで
-
防災講座を開催します
2018年5月1日(火)
大分大学減災・復興デザイン教育研究センターでは、地域の皆様に「防災を身近に感じて頂くため」大学キャンパスツアーとして防災講座と学食案内を行います。 講座の内容は、身近に発生する自然災害のお話やもしものケガや病気に備えた応急手当等、要望に応じて指導します。また、講座終了後は大学キャンパスツアーとして学食にご案内します。 ☆ 場 所 大分大学 旦野原キャンパス 産学官連携推進機構棟内 2F セミナー室 ☆ 日 程 毎週1回程度(10時から11時30分) ☆ 人 員 20名程度 ☆ その他 交通手段及び学食は各自でお願いします。 防災講座を希望される方は、以下の連絡先にご連絡ください。別途、詳細等を打ち合わせて、申込書をお送りいたします。 連絡先 大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター 電話 097-554-7333 担当 防災コーディネーター 板井
-
中津市耶馬渓町金吉で発生した山崩れ災害派遣終了について
2018年4月24日(火)
この度の土砂災害により被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げます。 4月11日に中津市耶馬渓町金吉で発生した山崩れの災害に関して発生当初から現地入りし,15日(日)より中津市長からの災害派遣要請にもとづいて,現地で捜索活動に伴う危険性について現地調査を行い,現地対策本部へ助言を実施してきました。そして4/23日(月)に捜索活動が終了したことを受け,減災センターもその役目を終えて,災害現場からの引き上げが完了しました。 災害現場では大量の崩積土に加え巨石や不安定な斜面の状況で捜索活動が難航しました。特に,二次災害の恐れのあるなか,連日連夜で懸命に捜索活動にあたった消防,警察,自衛隊,行政関係者,そして地元建設業協会の方々に深く敬意を表します。 今回の大規模な土砂災害に関しては,減災センターでは発生機構の解明に加え,捜索活動を伴う災害時の対応や復旧・復興過程についてさらに検証を重ねていきます。そして,引き続き,大分県内で発生する自然災害に対して,調査研究,防災・減災を通じた防災教育,そして地域支援活動を実施していきます。 なお,災害に関して,発生当時から捜索活動終了までの間,ドローンによる映像及び動画データを減災センターでは保存しております。災害対応,防災教育,学術研究のみ利用可能です。必要な方は減災センターまでお問合せ下さい。 <中津市耶馬渓金吉山崩れ災害派遣関係者> ・西園 晃 センター長(理事・医学部教授)災害派遣責任者 ・小林 祐司 センター次長(理工学部准教授:都市防災)災害派遣管理責任者:危機管理対応 ・鶴成 悦久 准教授(産学官連携推進機構:土木工学)現場責任者:発生機構・災害対応・土木分野対応 ・小山 拓志 准教授(教育学部:地理学)発生機構,地理・地質担当 ・西口 宏泰 准教授(全学研究推進機構:分析学)水質・地質組成分析担当 ・板井 幸則 防災コーディネーター(減災センター)自治体連携・災害対応担当 ・藤澤 靖(研究・社会連携課社会連携係長),杉田 智美(減災センター事務補佐員 )事務担当 <学外派遣協力> ・橋本 哲男 氏 (株)日建コンサルタントSIT事業部次長:空間情報担当 ・大島 郁夫 氏 (株)ソイルテック 専務取締役:応用理学・発生機構・地質担当 2018.4.22 AM6:53撮影
-
【第4報】中津市災害派遣要請にもとづく災害対応活動について
2018年4月16日(月)
中津市耶馬溪町で発生した土砂災害に関して,中津市長からの災害派遣要請をうけ,大分大学減災・復興デザイン教育研究センター(以下,減災センター)では現地調査を実施しながら,現地対策本部にて各種技術支援・提供・二次災害防止に関する助言等を実施しています。なお,減災センターでは(株)日建コンサルタント(大分市)橋本哲夫氏(測量),(株)ソイルテック大島郁夫氏(応用理学)の協力を得て,産学官の連携による現地対策チーム(土木,地理,理学,危機管理,測地,化学)を編成し,連日,現地の災害対応にあたっています。 以下,現地で利用可能な情報等を減災センターHPで公開し,関係各所にて現地捜索活動対応に関する情報の提供・共有・活用を図っております。 ※データ等を二次利用(捜索活動にあたる関係各所を除く)する際には大分大学減災・復興デザイン教育研究センター・(株)日建コンサルタントを明記してください。また,オリジナルデータ等が必要な場合は,減災センターまでお問合せ下さい 4/15撮影データ:UAVによる3D点群データ(Web上で断面,面積,距離等の計測が行えます) http://www.cerd.oita-u.ac.jp/uav2/yabakei20180415.html 4/16午前7時現在 災害現場 4/15 オルソデータ(PDF) 4/16 落石・崩落危険箇所マップ