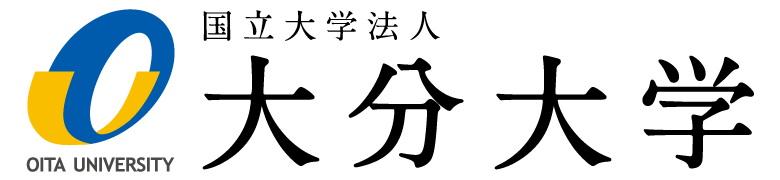-
防災シンポジウム in 日田 〜 九州北部豪雨からの教訓 〜 (内容・結果の公表)
2018年8月19日(日)
※一部更新作業中 防災シンポジウム in 日田 〜 九州北部豪雨からの教訓 〜 日時:2018年8月18日(土) 13:30〜17:00 会場:マリエールオークパイン日田 主催:国立大学法人大分大学 共催:日田市 大分高等教育協議会 後援:大分県 大分合同新聞社 九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター 企画:大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 一般社団法人 NINAU 地理空間情報活用に関する大分地区産学官連携検討会 協力:SAPジャパン株式会社 ESRIジャパン株式会社 株式会社ザイナス 8月17日,18日と日田市において,日田市内高校生と大学生によるフィールドツアー(8/17)とシンポジウム(8/18)を開催しました。 以下,シンポジウムの成果として公開いたします。それぞれの地域で「防災・減災」,そしてこれからの災害への向き合い方などの「きっかけ」や「ヒント」として頂ければと思います。 防災シンポジウム in 日田「九州北部豪雨からの教訓」 司会:岡野 涼子(一般社団法人NINAU 代表) 1.開会挨拶 大分大学理事(研究・社会連携・国際担当)・副学長 減災・復興デザイン教育研究センター長 西園 晃 日田市長 原田 啓介 様 2.特別講演 九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター センター長・教授 三谷 泰浩 様 3.学生提案 ★フィールドツアー(Youtube) その他の動画については以下をご覧下さい。 Link → CERD Youtube 動画リスト ※フィールドツアー行程(8/17) 日田市役所→大鶴地区・瀬部・大肥→豆田地区・花月川→小野地区→解散 ★ストーリーマップ また,フィールドツアーの内容やデザイン・シンキングを通じた学生提案を「ストーリーマップ」としてとりまとめ,発表を行いました。 Link → 防災シンポジウム in 日田 「学生提案」(自動再生) 学生提案 ムービー & ストーリーマップ 作成協力:SAPジャパン株式会社 ESRIジャパン株式会社 株式会社ザイナス 4.パネルディスカッション ■ パネリスト(PN) 日田市長 原田 啓介 様 日田市小野地区振興協議会会長 藤井 維清 様 日田市大鶴振興協議会会長 石井 勝誠 様 大分工業高等専門学校・准教授 工藤 宗治 様 ■ コメンテーター(CM) 九州大学大学院工学研究院附属 アジア防災研究センター長・教授 三谷 泰浩 様 ■ コーディネーター(CD) 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 次長(理工学部・准教授) 小林 祐司 (1)趣旨説明 災害が多発するなか(災害多発時代),これまでの考え方で良いのか? 一人一人が責任を持てる社会にしていかなければならない 若い世代の参画も求められる (2)学生提案へのコメント <PN/CMによるコメントおよび議論> 災害とどう向き合うかを考える必要がある。そのためにも,リスクを把握すること。 ひとりひとりが責任を果たすことが重要 災害に向き合う姿勢を見せる 地域に戻って大丈夫なのか? 高齢者(のみが)がこういった(防災)ことを考えるのはまっとうか? 担い手の育成が求められる 復興には時間がかかる 俺たちの故郷は俺たちが守る 技術者の不足により,災害の現場に人が足りない 我々が経験してきたことが役に立たないかもしれない 高齢化が進む中で自治を守っていけるのか → 新しい仕組みが必要 産業・流通の変化 生業のあり方から復興を考えなければならない 世代によってコミュニティの認識が異なる 高等教育のなかで,机上での知識が多いがダイレクトに響いているのか? 「コミュニティ」の本当の意味を理解しているか?あらためてコミュニティの在り方を考えないといけない。 現場の実際の空気感を感じなければわからないことがある 被災者の方とともに汗を流して作業しないとわからないことがある ボランティアに参加する意識,自発的に参加する意識を育む機会をつくる 昭和学園生徒がボランティアに行ったことでお店の人がお店をやり続ける勇気をもらった 若い子は自分が必要とされることを求めている・・・自己有用感 ※クリッカーの回答者数は概ね「150人」程度とお考え下さい。 【クリッカー0】 Q:今日はどうしても言いたいことがある! → はい = 15.0% いいえ = 85.0% Q:しかし,まぁ何で連休の最後やねん! → そう思う = 13.1% そうは思わない = 67.7% わからない = 19.2% (参加者の基本情報) Q:年齢 → 10代 = 1.0% 20代 = 2.0% 30代 = 1.0% 40代 = 17.2% 50代 = 37.4% 60代 = 29.3% 70代以上 = 12.1% Q:自宅 → 日田市内 = 75.8% 日田市外(県内) = 20.2% 日田市外(県外) = 4.0% Q:勤務地(日田市内の方のみ) → 日田市内 = 65.7% 日田市外 = 4.0% 無職 = 30.3% (学生提案への感想) Q:学生提案は興味深いものがあった → はい = 71% いいえ = 29% Q:防災・減災対策に若い視点は不可欠だ → はい = 96% いいえ = 4% (3)PD ▶視点① 災害対応のあり方とは? <PN/CMによるコメントおよび議論> 何よりも命を守ってもらいたい 市民の方には知ろうと努力してもらいたい 避難指示で逃げないという状態を考えなければならない 日頃から、高齢者どうしが助け合える仕組み作り なによりも自助努力が大切 五年前までは小野は大丈夫だと思っていた。五年前の災害時もう再び来ないだろうと思ったが,そうではなく小野の地域はどこも安全ではない。 道路が水害で全部だめになり,新しい公民館でみんなが助かった 自治会長の判断が素晴らしかった。自治会長への感謝。 各町内に2名以上防災士がほしい 「率先避難者たれ」・・・早期避難の重要性 知ろうという努力をする 臨機応変に判断することの大切さ 言わなければならない,伝えなければならない 情報について分かりにくいというのはその通りだと思う。したがって,避難勧告とはどういう状況かなどの紙を配ろうと思っている 県境を超えた情報が速やかに伝わるシステムの構築(災害だけに留まらず) リスクの把握ができており,自分の身近なことであるという情報の出し方をしなければならない 空振りな情報でも6割あたっていれば良い方 (会場から) 「教育が大切」,どういう風に教育をしていけばいいのか? 災害がいつ起こったのかによって被災状況が全く違う その時の状況によって避難のあり方が全く違う 親御さん・家族がいるのか?によって避難状況が違う 高齢者が住んでいて、若者は帰ってこれないという状況が生まれてしまった。孤立してしまう。 どういう人が地域にいるのかを把握していてほしい 小野振興協議会,小野小学校の存続について「いつ戻れるのか,また戻らないのか,あり方の検討を行っている 今後,学校再建に関して小野全体の共通認識として捉えなければならない 通学中の道の問題 学校の問題地域の避難の支援のあり方 災害リスクコミュニケーション マイタイムライン ⇒こういうことが起こったらこういうことをします!! ⇒家族会議につかう(じいちゃんはどうする父ちゃんはどうする?) 連絡が無くてもやっていけるように マイタイムラインは家庭のなか,地域のなかでも実践できる 家庭のなかの信頼関係が大事 信頼関係をつくり実践をしていく 学校にも(取り組むべき)責任がある 親だけではなく子供に考えてもらう宿題にすればいいのでは? 「経験に勝るものはない」 自分の身は自分で守る 災害から一年で避難訓練を行った ⇒ (予想外の)50人もの参加 実際自分がどういう行動をするかを実践してくれた人もおり,真剣に住民が考えていることがわかった 災害を経験したことはむしろ強みである (会場から) 防災無線について,同じ日田市内である地域とない地域なぜ差があるのか? 衛星回線を使う防災無線を各戸にと考えている ⇒ 有線が災害時意味をなさなかったため ※クリッカーの回答者数は概ね「150人」程度とお考え下さい。 【クリッカー1】 Q:これまでの雨,豪雨で被害に遭ったことがある → はい = 41% いいえ = 59% Q:身近な災害リスクをしっかりと把握している → はい = 72.3% いいえ = 27.7% Q:雨が降った際の対応行動について → 大雨警報などの「警報」が出たら避難をする = 4% 「避難準備・高齢者避難開始」で避難をする = 8% 「避難勧告」で避難をする = 36% 「避難指示(緊急)」で避難をする = 38% はっきり言ってどうしたら良いかわからない = 14% Q:今回の西日本豪雨の際,避難を行なった → はい = 12% いいえ = 88% Q:防災情報として最も重要だと思う情報端末・手段は → テレビ = 28% ラジオ = 9% 防災無線 = 18% インターネット(PCやスマートフォンも含む) =39% 近所や家族など人からの情報 = 6% Q:そもそも「情報」がわかりにくい → はい = 40% いいえ = 60% 【視点①のまとめ】 担い手の育成に加えて,コミュニティの真の意味を 早期避難,早期対応の重要性(地域で完結できる対応行動と支援の仕組み) 若い世代の参画 個人はもとより,家庭,地域それぞれでできることを進める ▶視点② 災害に対して責任を果たせる社会とは? <PN・CMからのコメント・議論> ハード整備は簡単にはできない(限界があること) どうやって情報を届けるかが課題 全員が共通の情報をとっているか否かで状況が変わってくる 情報の届け方について行政として取り組んでいきたいと考えている インフラ整備はもちろんだが、防災マップなど・・・行政を頼らず地域住民が率先して行う 地域住民の相互理解 若い人に災害を伝えていくことが大切 コミュニティの確保 宇和島の吉田地区はまだ復旧が進んでいなかった。⇒ボランティアのありがたさを改めて感じた ボランティアへの感謝 みんながお互いに助け合う社会にしていきたい 長期の責任を考える,1~2年たってどうなったか(復旧・復興のプロセス) 復旧作業を調べて,定点観測をしている 学生や次世代の人にいかに伝えるか,意識を共有するか 直後だけでなく長期にわたって(長いスパンで)考えていかなければならない 自分の命は自分で守る 出来ないことは助けあって ※犠牲になれという話ではなく,できるだけ早い避難を ハード整備はいくらやってもやりたりない 今が一番危険な状態であり,復旧中は被災前よりも弱く,危険な状態であることを知っておいて欲しい 強弱(必要なところに必要な手立てを)を持たせたハード整備 説明責任を持ったハード整備をしなければならない ハード整備には限界があるから,バランスを取りながら進めていく そこには行政と住民の相互の理解が必要であり,それが平時の信頼関係となり,災害時にも機能する 新しいコミュニティ・自治のあり方が問われている 社会の構成が代わっていくため,支える人たちが減っていく。少子高齢化で大きなリスクを抱えた人が増えてくる 住民自治組織(中津江などの例),どうやって組織が支えていくかが課題 行政と今後どういった関わりを持つのか 若い人は何らかの思いをもっていて,行動をしてるのではないか 若者には今までになかった感覚があるのではないか,新たな価値観がある 100年スパンが通じなくなってきている。10000年スパンといった覚悟が必要なのではないか。 住まい方自体を考え直さなければならないのではないか インフラ整備は人口増を基本に考えており,切り捨てないといけない部分があるのではないか 住めないけれども離れられない(のが実際) 生業の中で生きていかなければならない人もいるため,持っていた資産からお金が回ってくる仕組み 産業の在り方の政策を今後考えていかなければならない 稼ぐ場所・住む場所を確保することが求められ,土地の違う活用の仕方も 所帯の少ない自治会は班が成り立たず,限界集落は1人の役割が増えてしまう 自治会自体が今後どうなっていくのか?自治会の統廃合を考えなければならない 日田市163自治会ある。コミュニティをどう維持するか・・・現在隣保班の統廃合を行っている(既に6年前に統廃合を行った) 住み続けるためには安全性は必要だが、長年継承される伝統などを中心に考えることも必要 村地域の在り方を模索していかなければならない 個人個人で地域について考えていかなければならない それぞれに合った組織づくりが必要で,如何に地域を盛り上げていくのか ひとりひとりが「責任を取る」という覚悟が必要 自然現象のなかに人間が食い込んでいる。災害はおこる。「知らない」じゃ済まない。 災害を受けていない人も責任を果たさねばならない ※クリッカーの回答者数は概ね「150人」程度とお考え下さい。 【クリッカー2】 Q:もっと住民は地域の防災・減災に参画すべきだ → はい = 97% いいえ = 3% Q:我々の自治会は防災への意識が高い方だと思う → はい = 26% いいえ = 42% わからない = 32% Q:もっと若い世代の参画が必要だ → そう思う = 66.3% そう思わない = 4.0% わからない = 5.0% 期待したいが,期待できない = 24.8% Q:災害対応の責任は誰,どこにあるのか? → 各個人・各家庭 = 53% 地域(自治会や自主防災会) = 5% 行政(県・市町村) = 14% 国 = 3% 誰の責任でもない = 17% わからない = 8% Q:やっぱり「当事者意識」を持つことだ → はい = 100% いいえ = 0% Q:住民一人一人にも責任があると思う → はい = 92% いいえ = 8% 【視点②のまとめ】 新しい自治の仕組みやあり方 → 新しい地域づくりへ取り組む 地域づくりや活性化は防災だけではない ひとりひとりが責任を果たすことを社会的課題と理解するべき (4)CDによるまとめ 防災学術連携体の提言にも「あなたには災害の危険性を知る義務と自分と家族を守る責任がある」と述べられている。 自治会の再構築も「まちづくり」という観点からは求められる 防災・減災を「地域づくり」の一部として取り組み,今日的な地域課題に向き合うことも必要 一人一人がそれぞれの立場で責任を果たしていくこと,これをやっておけばいいということはない 住民一人一人にも不断の努力が求められている 何よりも,子ども達,若い世代にその「姿勢」を示すべきである・・・それが一つの責任でもある 【シンポジウムの感想】 ※クリッカーの回答者数は概ね「150人」程度とお考え下さい。 Q(役に立ったか)(役に立ちそう) → はい = 92% いいえ = 3% わからない = 5% 〜最後に〜 本シンポジウムとフィールドワークは多くの方々ご協力を頂きながら実施することができました。この場をお借りしまして,心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。 初日のフィールドワークでは,地域住民の皆さん,日田市,国土交通省に大変お世話になりました。高校生や大学生にとっては,現地の生の声を直接伺うことができ,また「空気感」を感じることができたのではないでしょうか。 翌日のシンポジウムでは,大学生を中心とした作業により「学生提案」という形で,今後の防災・減災対策について彼らの「生の声」をお届けでき,また今後も残る「かたち」にできたと思っています。 シンポジウムに参加された方々はどのようにお感じになったでしょうか。彼らはもっと「関わりたい」と思っているのではないでしょうか。でも「関わり方」の難しさが「コミュニティ」にあるのかもしれません。「コミュニティ」とは何か。机上だけではわからないことが多いはずです。「コミュニティ」を知る・学ぶ上で重要なことは「現場で何を感じるか」にあると考えています。我々大人はその「機会」や「場」を提供する役目があるのだと思います。それが「担い手」の育成にも繋がっているはずです。「自己有用感」という言葉も出てきました。確かに皆「役に立ちたい」と思っているはずです。当然ながら,個人でも積極的に関わって行くことが求められます。 この「コミュニティ」を知り,地域課題を見つめ,その方策・取組を提案し,(失敗したとしても,新たな取組を)実践し続けて行くことが,巡り巡って「防災・減災」のあり方に繋がっているのではないでしょうか。そこを突き詰めていけば,「責任」について議論する必要は(そもそも)ないのかもしれません。 「成熟した社会」という言葉が使われることがあります。果たして社会は「成熟」しているでしょうか。「成熟した社会」とは,地域社会の持続性が確保され,・・・という言い方は小難しいのでもう少し噛み砕いて言えば,「今生きる大人(達)が,次の世代(子ども達,若者)に胸を張って今の地域や社会を引き継げられるものとなっている」ということではないでしょうか。そこに「防災・減災」,さらにその先の「安全・安心」が含まれているべきものなのだと思います。 我々はあまりにも便利になったが故に,危機管理能力が(もともと低かったものが)極度に低下していると言われています。このような状況を打破するためにも,防災教育をはじめとした社会が関わる「教育」の役割は大きいのです。「教育」の形も様々です。家庭,地域,学校,広くは地域社会全体,国における「教育」といった,それぞれ役目,役割が異なる教育の「かたち」があります。それぞれの立場で必要な「教育」を施していく必要があります。それぞれの立場と役割においてです。それが「責任」でもあります。何かを残し,何かに繋がる「教育」こそが本当に必要な「教育」であるはずです。その際,一緒に考える「共考」の姿勢を忘れてはなりません。 シンポジウムのなかでも発言をしましたが,今日の災害は我々の経験が全く役に立たなくなっているような様相を呈しています。では,我々も社会も変えるべきところは変えなければ対応できなくなってしまうのではないか。そんな危機感を共有し,新たな取組へと繋げていかなければなりません。今までできなかったことを実現するのが,今日的な防災・減災なのだと思います。原田市長の言葉にもあった「新しい自治組織」もそのなかの一つの挑戦とも言えます。これらも一つの「責任」です。 今回のシンポジウムでは「対応」と「責任」というキーワードで議論,情報共有を行いました。あらためて我々自身に問いかけてみる必要があります。 「地域への関わりや安全・安心に対する「責任」を果たしているだろうか?」 「子ども達に自信を持ってその姿勢を見せることができるだろうか?」 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター【CERD】
-
【速報】「防災シンポジウム in 日田」を開催しました(8/17-18)
2018年8月18日(土)
8月17日,18日と日田市において,日田市内高校生と大学生によるフィールドツアー(8/17)とシンポジウム(8/18)を開催しました。 シンポジウムでの議論の内容・結果については,後日詳細をホームページに掲載をしますが,フィールドツアーの様子,日田市内高校生や大学生のコメントをまとめた動画を速報として掲載します。この動画やストーリーマップはシンポジウムの中で「学生提案」として公開されたものです。 ★フィールドツアー(Youtube) その他の動画については以下をご覧下さい。 Link → CERD Youtube 動画リスト ★ストーリーマップ また,フィールドツアーの内容や学生提案を「ストーリーマップ」としてとりまとめ,発表を行っています。 Link → 防災シンポジウム in 日田 「学生提案」(自動再生) 学生提案 ムービー & ストーリーマップ 作成協力:SAPジャパン株式会社,ESRIジャパン株式会社,株式会社ザイナス
-
OBS大分放送と減災・防災に関する連携協定を締結しました
2018年8月9日(木)
8月7日に大分大学減災・復興デザイン教育センターCERDとOBS大分放送では大分県内の減災・防災に関する協力を深めるため連携協定を締結しました。 締結式では北野学長とOBSの永田取締社長が協定書に調印し、災害の調査や研究、それに取材の成果を相互に活用するほか、防災教育などを進め情報発信を強化します。
-
臼杵っ子サマーキャンプ(防災キャンプ)を実施しました
2018年8月7日(火)
8月2日(木)と3日(金)に野津中央公民館(臼杵市)にて防災教育の1つとして臼杵っ子サマーキャンプ(主催:臼杵市 社会教育課、後援:大分大学 減災復興デザイン教育研究センター)を行いました。この防災キャンプの目的として「平成30年7月豪雨」や「大阪北部地震」など近年多発する自然災害 から『自分の命を守るための安全教育』『助け合いやボランティア活動などの共生の心を育む』ことを目的に実施しました。開催初日はお互いをよく知ろうという事でオリエンテーションを行いました。その後、簡単に防災について座学を行いグループに分かれて屋外の危険な場所がないか調査し危険と感じた場所を写真やメモにまとめ防災マップを作成して各グループごとに発表をおこないました。宿泊する際に段ボールを使用して簡単な間仕切りを行い避難所体験を行いました。2日目は段ボールを使っての簡易トイレやスリッパなど非常時に役に立つ工作を行いました。 2日間と短い期間でしたが、この防災キャンプを機会に防災・減災への考えを深めていただけたらと思います。 防災についての座学 危険場所の調査 各グループごとによる危険と思った場所の発表 実際に作成した防災マップ 段ボールを使っての避難所体験 段ボールを使った簡易トイレとスリッパの工作風景
-
「備えるチカラ~OBS防災・減災キャンペーン」に減災センターが協力
2018年7月31日(火)
減災センターではOBS大分放送が実施中する「備えるチカラ~OBS防災・減災キャンペーン」に協力しています。 頻発する豪雨災害や地震など,一人ひとりが防災への備えを改めて考え,そして防災への意識を高めて行くことが重要性です。 ■備えるチカラ~OBS防災・減災キャンペーン~はこちらをご覧ください。 http://www2.e-obs.com/cp/bousai_gensai/
-
「防災シンポジウムin日田-九州北部豪雨からの教訓-」を開催いたします。
2018年7月30日(月)
平成30年8月18日(土)13:30より日田市「マリエールオークパイン日田」にて「防災シンポジウムin日田」を開催いたします。 ※7月26日(木)に学長記者会見を行い,その会見の一部で「防災シンポジウムin日田ー九州北部豪雨災害からの教訓ー」開催を発表しました。 このシンポジウムは今年で9回目を迎え,大分大学と関係市町村,そして高等教育協議会が共催し,さらには関係機関との連携によって行われています。本年度は昨年度に水害で甚大な被害を受けた日田市にて「九州北部豪雨災害からの教訓」をテーマに開催いたします。 ご周知の通り,昨年の九州北部豪雨災害をはじめ,台風18号による風水害,そして本年4月に発生した中津市耶馬渓町の山崩れなど,甚大な被害が県内各地で発生しました。そして今年7月には西日本を中心とした豪雨災害が発生し,200名を超える多くの尊い命が失われました。全国的に頻発する災害に対して改めて災害とは何かを問い,災害にどう向かいあうかを真剣に考えていくことが,社会的に求められる最も重要なテーマになりつつあります。 防災シンポジウムは「災害対応 防災対策はどうあるべきか」「課題は何か」を共有し,地域防災や減災・復興を考える“きっかけ”となることを目指します。 今回,新たな試みとしてシンポジウムでは学生提案を行います。この提案を行うにあたり,前日の17日(金)に豪雨災害によって被災した日田市内の各地を巡る「フィールドツアー」を実施します。ツアーでは,被災した地元の住民や行政の他,支援ボランティアや復旧に当たった地元建設業と交わります。ツアーを通じて感じた想い,復興や防災・減災に向けた地域づくりに関しての考え方を,学生や地元高校生の視点から提案します。 幾度なく押し寄せる災害に対して,我々は何を学んだのかを改めて考え,次の世代への継承も含めた,実りあるシンポジウムを開催いたします。 多くの方のご参加をお待ちしております。 7月26日(木) 学長記者会見の様子
-
ArcGIS Online体験セミナーの実施
2018年7月27日(金)
7月25日(水)にESRIジャパン株式会社様より藤春様、石原様を本大学にお招きして本学生及び教職員を対象にArcGIS Online体験セミナーを行いました。 最初にArcGIS Onlineの説明と実際にどういった際に活用できるのかを簡単に説明していただき、 その後にノートPC又はタブレットを用いて実際にアプリケーションがどういう風に表示されるのか体験した後に簡単な実習を行いました。
-
大分市横尾中筋防災会において子ども向け防災講座を開催
2018年7月23日(月)
7月21日(土)に大分市大分市横尾中筋防災会での子ども向け防災講座を開催しました。 今回は大学生・大学院生の皆さんが中心に運営する2時間ほどの講座となりました。 紙ぶるる,減災かるた,超自然クイズの大きく三つの内容を実施し,楽しく防災を学ぶ機会が提供できたと思います。 子ども達だけでなく,保護者の方も一緒に取り組んで頂きました。
-
大分県広報TV「アライグマ被害の防止に向けて」について
2018年7月12日(木)
特定外来生物アライグマの生息域が全国的に拡大し,生態系や農作物の被害が増加しています。今後,アライグマの増加により,食害や生態系への被害の他,ウイルスの媒介等が懸念され,未然に防ぐ取組が重要とされています。 平成30年度に入り,大分県では県北西部地区のアライグマ防除推進の取組が始まりました。減災センターでは,アライグマ防除情報の共有と分布拡散予測について,大分県生活環境部自然保護推進室やNPO法人おおいた環境保全フォーラムと連携した研究事業を始めております。 6月16日(土)に大分県広報TV「ほっとはーとOITA」(TOS放送)で放送された「アライグマ被害の防止に向けて」について,これらの連携事業に関する内容が放送されています。特に減災センター兼担教員(医学部助教)の奥山めぐみ先生(獣医学,野生動物学)が事業に関するDNA分析や分布拡散等の研究内容について紹介されています。 おんせん県おおいた!チャンネル 大分県広報TV「アライグマ被害の防止に向けて」 http://www.onsenkenoita-ch.com/tos/detail/3031
-
豪雨による大分県内の被害調査について
2018年7月9日(月)
(平成30年7月豪雨災害について) このたびの豪雨によって,お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに,ご遺族に心からお悔み申し上げます。そして,被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 (豪雨による大分県内の被害調査について) 豪雨によって,大分県内でも人的被害をはじめ,住宅や道路,河川被害や土砂,農林被害に関して被害が発生していました。※詳しくは大分県「平成30年7月5日大雨警報に関する災害情報について」をご覧ください。 減災センターでは,この度の豪雨災害に関する大分県内の現地調査について関係機関(自治体等)と連携を図りながら以下の通り調査を実施しております。 ①杵築市山香町倉成で発生した道路陥没現場(他一件) 7月9日(月)に減災センターでは杵築市建設課と合同で市道日出大田線(山香町倉成)(図-1)で発生した道路陥没個所の調査を行いました。 現場は杵築市山香町から太田村に接続される市道で,鋸山トンネル出口から山香町方向に約1km離れた個所で道路が陥没し(写真-1,2),山香町から太田村へ走行してきた車が陥没箇所に転落するなどして,人的被害が発生しています。 現場付近の地質は花崗岩が風化した真砂土(まさ土)が広がっており,陥没した道路の路体(地山地質)は真砂土で構成されていました。ただし,盛土部は流亡しており土質材料については不明です。陥没した箇所は道路縦断・横断勾配(形状)から降雨により道路表面及び周辺地帯からの排水が路面から路床に集中した可能性が指摘されます。特に真砂土は水に弱いとされており,この地層で構成された道路路体(地山)と路肩付近から盛土部の土層境界部に降水が流れ込み,道路陥没(土砂流出や斜面崩壊)に至ったと考えられす。 杵築市や国東町(特に県北部)には花崗岩が風化した真砂土が分布しており,真砂土は含水比が多くなると非常にもろく,崩れやすい性質をもっています。広島県では真砂土による土石流やがけ崩れなどの土砂災害が発生するなど,たびたび地質の危険性が指摘されております。 杵築市では市道竜ヶ尾床並線(写真-3)でも同様の道路陥没が発生しており,減災センターでは杵築市の依頼により現地調査を行いました。 なお,現地における迂回路等につきましては,杵築市建設課ホームーページをご覧ください。 http://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/16/ 図-1 道日出大田線(山香町倉成) 写真-1 道路陥没現場(山香⇒太田方面を望む) 写真-2 道路陥没現場(太田⇒山香方面を望む) 写真-3 市道竜ヶ尾床並線