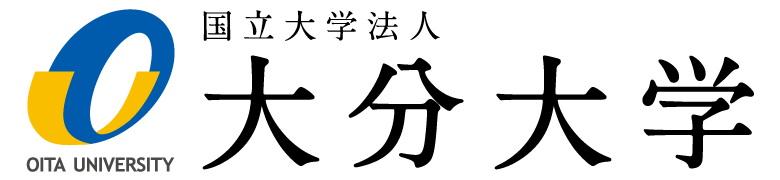-
【記事】災害発生時の迅速かつ正確な初動対応を促すための情報活用プラットフォーム
2019年6月12日(水)
減災センターでは,(株)ザイナス(大分市)とSAPジャパン(株)(東京都)との共同研究「防災・減災のための情報活用プラットフォームの構築(プロジェクト:CERD EDiSON)」を進めております。 2019年6月11日付けにて,共同研究先企業であるSAPジャパン(株)のBlogに「災害発生時の迅速かつ正確な初動対応を促すための情報活用プラットフォーム―減災社会の実現と協働を目指して―」と題して,小林センター長,鶴成センター次長,山本客員研究員(ザイナス 取締執行役員本部長),吉田客員研究員(SAPジャパン デジタルエコシステム統括本部) によるEDiSONプロジェクトに関する記事が掲載されました。 SAPジャパン(株)Blog記事 https://www.sapjp.com/blog/archives/24967 本プロジェクトについては2019年7月11日のSAP NOW基調講演で小林センター長による「Innovate with Purpose~ 迫り来る自然災害への対応を深化させるために」にて発表いたします。 https://now.sapevent.jp/register/
-
『OBS 防災・減災セミナー』【6/2(日)開催】のご案内
2019年5月21日(火)
6月2日(日)13:30-15:00に「OBS 防災・減災セミナー」がコンパルホールにて開催されます。講演には大分大学減災・復興デザイン教育研究センターから小林センター長(理工学部・教授)が登壇予定です。休日ですが,ぜひお越しください。 なお,大分大学減災・復興デザイン教育研究センターはOBSの「防災・減災キャンペーン」に協力し,2018年8月9日にはOBS大分放送と減災・防災に関する連携協定を締結しています。
-
【記者発表】国土交通省国土地理院九州地方測量部との連携・協力に関する協定の締結について
2019年4月23日(火)
同時発表:国土交通省国土地理院九州地方測量部 減災センターと国土地理院九州地方測量部は、それぞれが保有する地理空間情報の相互利用、防災・減災に向けての協力の強化、調査研究及び防災教育について連携を図るため、協力協定を締結します。 減災センターと国土地理院九州地方測量部は、これまで「地理空間情報活用推進に関する九州地区産学官連携協議会」の活動を通じ、地理空間情報に関する意見交換や情報共有を重ねてきました。また、九州地方測量部は災害対策基本法に基づく指定地方行政機関として、さまざまな災害に関する被災状況調査や地理空間情報の収集及び提供を行っています。大分県域において近年対応した災害としては、平成29年7月九州北部豪雨及び同年9月台風第18号の影響により大分県内を相次いで襲った水害や平成30年4月に大分県中津市で発生した土砂災害があります。 昨年1月、大分大学に減災センターが常設化されたことから、大分県域の安全・安心な地域づくりに寄与するため、保有する災害関連情報の相互利用、地域防災力向上に資する取組、調査研究及び防災教育に関する連携・協力について両者が合意し、以下のとおり協定調印式を挙行します。 なお、本協定は、国土地理院の地方測量部と大学が締結する全国で初めての協定となります。 調印式 日 時:平成31年5月20日(月) 13:30~14:30 場 所:大分大学産学官連携推進機構 2階セミナー室 取 材: 公開(調印式終了後、質疑応答の時間を設けております。) ※カメラ撮りは冒頭から可能です
-
『改訂版 おおいた減災かるた』 ダウンロードサイトについて
2019年4月23日(火)
減災センターでは、子どもから大人までの幅広い世代が、楽しみながら災害やその対策について学ぶことを目的に『改訂版 おおいた減災かるた』を制作・発行しました。 また、以下のサイト(減災センターHPのサイトバナーを参考)にて「かるた」(PDF)をダウンロードし、厚紙に印刷するなどして各自でご利用できるようにしていますので、是非、ご利用ください。 http://www.cerd.oita-u.ac.jp/gensaikaruta/ 『おおいた減災かるた』は、平成27年3月に教育学部川田 菜穂子准教授(教育学部/減災センター兼担教員)が中心となって制作し、発行後も、大分県内および日本全国各地で地震や豪雨、台風、土砂崩れなどの様々な災害が頻発していることから、近年に発生した災害の経験や教訓をふまえて、読み句や解説書などの内容を一部改訂し、より大分らしい特色をもつ内容として新たに制作したものです。
-
「フカイロ!」(NHK)に出演&「大分県災害データアーカイブ」について
2019年4月21日(日)
2019年4月19日(金)に放送された「フカイロ! 大分県災害データアーカイブ~“キロク”と“キオク”を生かして」(※「フカイロ!」は4月からの新番組)にセンター長の小林が出演しました。 この放送では,小林研究室が作成に協力した「大分県災害データアーカイブ」の紹介や,県内で頻発する災害への向き合い方や考え方などが,過去の災害を例に解説されました。 NHK大分放送局のホームページから「大分県災害データアーカイブ」が閲覧でき,また,県民の皆さんから大分県内で起きた災害の情報をお寄せ頂くサイトも公開されています。情報提供に是非ご協力ください。 ★大分県災害データアーカイブ https://www.nhk.or.jp/oita/saigai-data/index.html 大分県災害データアーカイブ投稿フォームについては,NHK大分放送局のトップページからアクセスしてください。 NHK大分放送局:https://www.nhk.or.jp/oita/
-
減災カフェ「防災・減災VR」を開催
2019年4月5日(金)
2019年4月4日(木)臼杵市観光交流プラザにおいて,減災カフェ「防災・減災 VR」を開催し,約70名の方に参加を頂きました。 第1部 VR×紙芝居×簡易地震体験(対象:〜小3まで) 第2部 VR×ドローン(対象:小4〜中学生) 第3部 VR×ドローン×簡易地震体験 ※自由に体験 当日は,幼稚園園児,小学生から中学生,そして大人の方々が,紙芝居,VRゴーグルを使って九州北部豪雨・地震・火災の映像を体験しました。また,第2・3部ではトイドローンの操作体験,ドローンシミュレータの体験もして頂きました。 本ワークショップは,大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの主催,SAPジャパン株式会社および株式会社ザイナスの共催により実施いたしました。 また,実施にあたりご協力を頂きました関係機関に厚く御礼を申し上げます。
-
News Letter vol.2 ( Apr., 2019)を公開しました
2019年4月5日(金)
News Letter vol.2を公開しました。 今回の特集は「大分大学医学部附属病院災害対策室の活動」です。また,火山防災セミナーなどの報告も掲載しています。 メニュー「刊行物」→「News Letter」 News Letter vol.2(Apr., 2019) PDF
-
減災・復興デザイン教育研究センター人事について(お知らせ)
2019年4月1日(月)
減災・復興デザイン教育研究センターでは4月1日付けで,下記の通り人事異動が実施されました。 記 <減災・復興デザイン教育研究センター部門 准教授 次長 及び 主担当教員(配置換)> (新任者) 鶴成 悦久(つるなり よしひさ)(産学官連携推進部門 准教授より配置換) ※鶴成准教授は産学官連携推進機構産学官連携部門長を兼務する。 <減災・復興デザイン教育研究センター> (新任者) 事務補佐員 美﨑 世利奈 以上
-
CERDのロゴをリデザインしました
2019年3月11日(月)
減災・復興デザイン教育研究センターのロゴをリデザインしました。 センターの活動の大きな柱である − 「災害調査」「防災教育」「復興デザイン」 − この三つを積み重ねたイメージに加え,センターが推進する「地理空間情報の活用」のイメージをレイヤーの形で表現しました。 様々な情報や手段を組み合わせて,地域の安全・安心に貢献できるような活動の展開,情報の提供を進める − このようなイメージをもてるロゴとしました。 (新しいロゴ) (説明用イメージ)
-
福島復興支援イベント「しんけん、ふくしまからはじめよう」 に出展
2019年3月11日(月)
減災・復興デザイン教育研究センターは,2019年3月10日(日)10時~14時にJ:COMホルトホール大分前ひろばで開催された福島復興支援イベント「しんけん、ふくしまからはじめよう」において,ドローンシミュレーター体験のブースを出展しました。 ブースでは,シミュレーターの他に,九州北部豪雨をはじめとした災害でのドロ−ンの活用状況や撮影された映像などを展示しました。